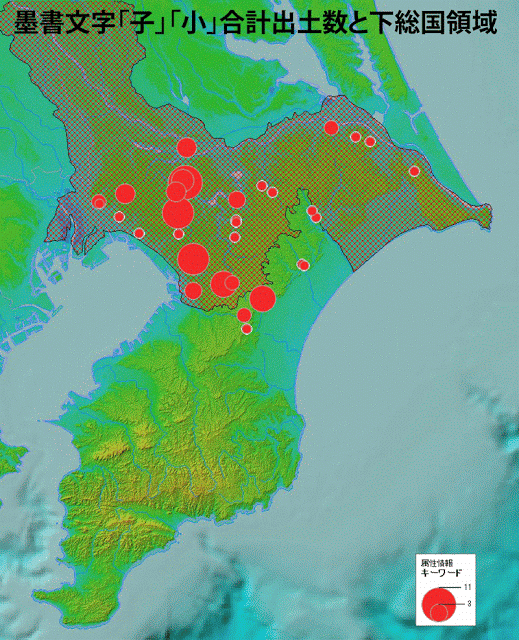縄文土器学習 484
2020.10.15記事「千葉市有吉北貝塚の遺物と遺構」で、内野第1遺跡では製糸(繊維製品)が交易に関する主な生業になっていることがわかりましたが、その検討の中で円盤状土器片の役割について合理的空想(?)ができるようになりましたので、メモしておきます。
1 円盤状土器片の使い方(空想)
円盤状土器片を使って大麻繊維から糸素材を作る様子(空想)
大麻線維を微細なレベルで細長く裂いたものの両端を左手でつまみ、輪の下に円盤状土器片を乗せ、右手でクルクルまわします。それにより繊維に撚りが生まれます。円盤状土器片を外せば糸素材が出来上がります。
円盤状土器片
千葉市内野第1遺跡発掘調査報告書から引用
3㎝~4㎝程度のものが多く、手で回しやすい大きさです。
2 糸素材を使った糸の作り方(空想)
糸素材を2本あるいは3本紡錘車で撚って糸そのものを作ったと想像します。
最初に長さの異なる2本あるいは3本の糸素材を紡錘車で撚り、1本の糸素材が途切れた時、新たな糸素材を別の1本あるいは2本の糸素材に水(あるいはより粘性のある液体)をつけながら揃えて一体化して撚りを続けます。糸素材の水分・表面状況によっては水を使わなくても新たな糸素材を撚りに加えていくことができる可能性があります。このようにして、次々に糸素材を加えていけば、紡錘車で長い糸(糸素材2本あるいは3本の撚り糸)を作ることができます。
紡錘車(紡輪)
千葉市内野第1遺跡発掘調査報告書から引用
軸(紡茎)は木製のため出土していません。
紡錘車に開いている小孔はそこにヒモを通して紡錘車と軸を硬く結び、軸の回転と紡錘車の回転を一体化させる機能を担っています。宮原俊一「重たい紡錘車 -縄文晩期の有孔円板形土製品について-」(2020、「日々の考古学3」、六一書房)
3 参考 紡錘車の軸受け
紡錘車の軸(紡茎)下端が安定するように軸受けが使われ、それが次の出土物「有孔円板形土器片」であると想像します。
有孔円盤形土器片
千葉市内野第1遺跡発掘調査報告書から引用
4 感想
この記事は全て頭のなかで空想した事柄です。これで済んでしまっては学習になりませんから、大麻繊維と土器片と紡錘車(のようなレプリカ)を入手して、実験的にこの空想が成り立つか検証することにします。もし実験的にこの空想が成り立てば、それが証拠となる証明にはなりませんが、円盤形土器片意義学習は確実に前進します。