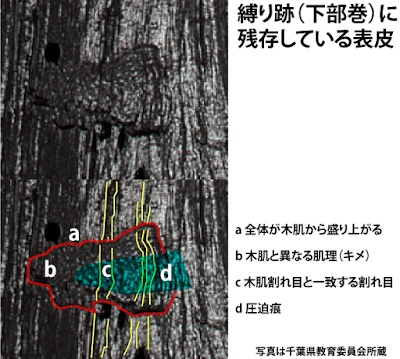西根遺跡出土「杭」に関わる杭及び発掘写真(未公表写真を含む)を千葉県教育委員会から入手し、検討しています。
「杭」そのものの写真を一瞥するとこれまで観察できなかった多数の特徴を観察することができます。その検討は追って行います。
これまでは発掘状況写真の分析を行い、写真に写る出土物が「杭」であり、その出土場所(1m×1mグリッド内における位置)を平面図の上で特定できました。
この記事では発掘状況写真から判読できる貴重な情報を検討しました。
1 出土物「杭」以外の丸木
次に1枚の発掘状況写真の判読結果を示します
4C09グリッド(縄文時代流路河床)発掘情報写真判読 1
B、Cとして出土物「杭」以外にそれに似た丸木の存在が判ります。
B、Cは発掘調査では自然木として処分され、出土物にはならなかったものと考えます。
Cは短いので何ともいえませんが、AとBは形状が類似し、ともに祭壇としてつかわれたイナウであると想定します。
D、Eは土器片の下及び中における粒状物のある黒い土層断面です。この黒い土層断面には黒い粒多数と木片断片がいくつも観察できます。この土層断面は拡大して下で検討します。
F、G、Hは発掘調査報告書で褐灰色粘質土と記載されている河床構成地層であると考えます。縄文海進の海の時代に堆積した地層であり、この場所が縄文時代後期の戸神川河床となった時に露出したものであると考えます。
写真の全体状況は次のように判読することができます。
1 褐灰色粘質土の戸神川河床面の上に「杭」、丸木が存在している場所がある。
2 同じ河床面に黒い粒多数と木片断片のある黒い土層が乗り、その上にその土層と土器片が混じった層が乗っている場所がある。
2 粒状物のある黒い土層
写真を拡大してより詳しく粒状物のある黒い土層を観察しました。
4C09グリッド(縄文時代流路河床)発掘情報写真判読 2
Aは河床面と土器片の間にある土層で黒い粒状物から構成され、所々に木枝の丸い断面(あるいは断片)が観察できます。
焼かれた獣骨の破片と炭(骨を焼いた木片の燃えカス)および燃え残った木片のように観察できます。
骨片と炭(及び燃え残り木片)が土器片層の下にあることから、焼骨行為が先でその後土器破壊行為があったと考えることができます。
Bは土器片と粒状物のある黒い土層が混じった層です。土器が破壊された時、土器片とその下にあった骨片と炭(及び燃え残り木片)の層が混じったものと推定することができます。
Cは発掘面(おそらく褐灰色粘質土層の上面、つまり河床面)に散らばる粒状物です。カドが丸いものは炭が多く、カドが尖っているものは骨片でが多いと想定します。
d、e、f、gは木片です。焼骨をつくった時の焚火につかった木枝の燃え残りであると考えます。その細さから上流から流れ着いた木片や付近に自生していた木(ヤナギ類など)がその始原であると想像します。
骨を焼くための焚き木は細く、祭壇用イナウはそれより太いという特徴の違いがあることも判りました。
この記事の写真判読では、「杭」以外にも同様の丸木が存在していたことと、焼骨行為の後その場所で土器破壊行為があったらしいことについてメモしました。