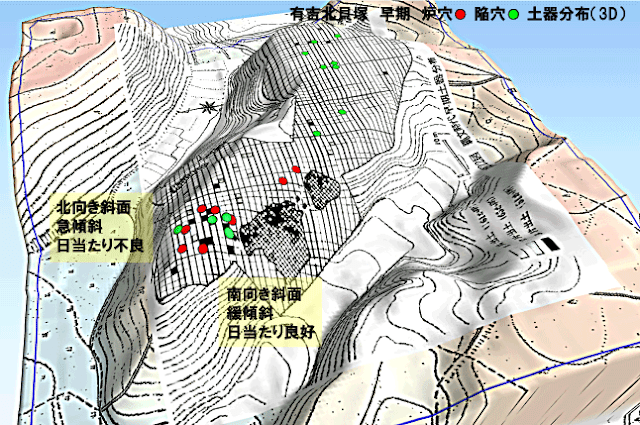縄文骨角器学習 1
千葉県立中央博物館令和2年度企画展「ちばの縄文」で展示された縄文中期箆状腰飾(千葉市有吉南貝塚)の3Dモデルを作成して観察しました。関連土器を含めて以前から気になっていた遺物です。
1 縄文中期箆状腰飾(千葉市有吉南貝塚) 観察記録3Dモデル
縄文中期箆状腰飾(千葉市有吉南貝塚) 観察記録3Dモデルイルカ類下顎骨製
埋葬関連遺物
撮影場所:千葉県立中央博物館令和2年度企画展「ちばの縄文」
撮影月日:2020.12.09
ガラス面越し撮影
3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v5.016 processing 54 images
展示の様子
展示の様子
説明パネル
関連土器
3Dモデルの動画
2 メモ
・向かって右側の穴が割れて、別の穴を補修して開けていますから、この腰飾は長期間使われていたことがわかります。
・詳しく観察すると下部に三角状の掘り込みが2ヶ所あるほか、刺突点に沿って浅い掘り込みが各所にあります。
・中央より少し下に表面が断続的に直線状に表面が削られた模様があります。この製品に意識してつけられたものであると考えます。この腰飾りを付けている人物が、祈願のために腰飾りに模様(傷)を付けたと考えることが合理的であるように直観します。
・赤い色が左穴付近の刺突点付近で観察できます。染料の色であるようです。
・青い色も各所に観察できますが、染料の色であるのか、骨の色(の画像の写り)であるのか、確認できません。
・これらの観察から、模様と色をある程度復元することが3Dモデルと撮影多数写真からだけでも可能かもしれません。