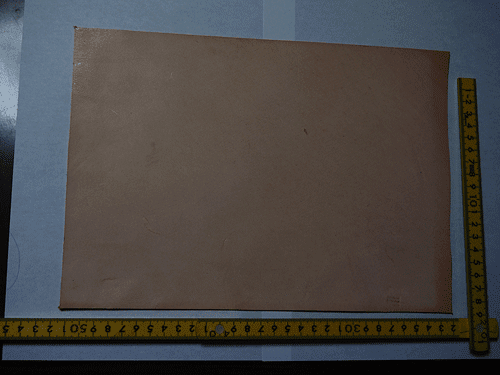縄文社会消長分析学習 109
有吉北貝塚北斜面貝層に関して発掘調査報告書データの分析が進んでいます。この活動の中で、いろいろな事実が判ってきました。まだ途中ですが現在までの知見に基づいてこれまでイメージしてきた貝層成立メカニズムを作業仮説としてまとめてみました。今後の分析作業を効率化するための仮説であり、不都合な点が判れば、躊躇なく加除修正するレベルの仮説です。
1 発掘調査報告書データ分析で判った事実など
分析作業で判った事実などを断面図・平面図作業画像にメモしました。
断面図・平面図作業画像メモ
1-1 北斜面貝層の位置
北斜面貝層は台地面と谷津谷底の間にある斜面の途中に発達する箱形窪地地形に形成されています。箱形窪地地形のガリー主流路左岸側(西側)だけにすっぽり収まっています。
住居近くの斜面に単純に貝を捨てたのではありません。特異な箱形窪地地形を意識してそこにだけ貝塚を形成しています。
参考 有吉北貝塚における北斜面貝層の位置
1-2 北斜面貝層の分布
箱形窪地地形の中に南北方向にガリー主流路(おそらく普段は空川)があり、その主流路を越えて貝を捨てていません。
なおガリー主流路堆積物は流心付近で明瞭に貝塚堆積物と土層に分かれます。(画像メモC参照)
参考 ガリー主流路流心を境に左右で堆積物が異なる様子
1-3 ガリー侵食地形と崩落物堆積地形
箱形窪地地形の貝塚形成前の地形は上流側はガリー侵食地形、下流側は崩落物堆積地形であると断面図や発掘写真から想定できます。ガリー浸食地形はその谷底に10群・11群土器(加曽利EⅡ式土器)をメインにして、集落最終期土器(12群土器…加曽利EⅢ式土器)を含む大形土器片層が存在します。この事実からガリー侵食地形は12群土器(加曽利EⅢ式土器)頃までアクティブであったと推定できます。つまりガリー浸食地形は加曽利EⅡ式~EⅢ式期頃急発達した可能性があります。一方、崩落物堆積地形は更新世の化石谷津であると想定します。(画像メモのAとB参照)
参考 貝塚形成直前地形の想定
1-4 貝層のほとんどが破砕貝による混土貝層と混貝土層
貝層はほとんどが混土貝層と混貝土層であり純貝層はとても少なくなっています。また純貝層以外の貝は破砕されている率が高くなっています。つまり貝層は、意図的に貝を破砕し、意図的に土と混ぜ、それを意図的に斜面や谷底に隈なく設置して、箱形窪地地形の集落側を充填するような様相を呈しています。
画像メモAではガリー侵食地形谷頭部に混土貝層と混貝土層が充填していますが、土器や獣骨の出土状況写真をみると混土貝層と混貝土層を下から積み上げて充填したもで、上から投げ込んだものではないような印象を受けます。
1-5 大形土器片
箱形窪地地形谷頭の少し下流から中央付近にかけて、基底で流路を覆うように廃用大型土器を破壊して作られる大形土器片が層を成しています。その大形土器片のメインは11群土器(加曽利EⅡ式土器の後半)ですが、12群土器(加曽利EⅢ式土器)も含まれています。12群土器は集落最後の土器群です。
参考 大形土器片の分布
1-6 縄文後期までのガリー侵食痕跡
第2断面には混土貝層・混貝土層が形成された後で後期貝層が形成される前までにガリー侵食を受けた痕跡が残されています。
縄文後期までにガリー侵食を受けた混土貝層・混貝土層の様子
2 北斜面貝層形成のメカニズム(作業仮説)
ア 11群土器頃(加曽利EⅡ式後半頃)箱形窪地地形でガリー侵食が突然発生し、集落中心部台地地形崩壊という災害危険性が顕在化しました。
イ 集落として災害防止のために土木的対処を含む取り組みを意思決定したと考えます。
ウ ガリー主流路の下方侵食防止のために、一部区間に廃用大型を持ち込み破壊して大形土器片をつくり、主流路の上に並べました。現代防災工事における床固工と類似している工事です。廃用大型土器を現場で破壊する活動は祭祀的活動であったと想像します。大形土器片と一緒にイノシシ頭骨、下顎骨が複数出土しています。
エ ついで、破砕貝を土と混ぜた混土貝・混貝土を多量につくり、それをガリー侵食地形に充填する活動を精力的に行いました。
オ さらにガリー侵食地形のみならず隣接する崩落物堆積地形にも混土貝・混貝土及び純貝層を堆積させ、箱形窪地地形全体を埋め立てるような活動を行いました。
カ この結果、ガリー浸食地形の進展は防止されました。
キ 12群土器(加曽利EⅢ式土器)を最後に集落は消滅しました。
ク その後、後期貝塚が形成されるまでの間に充填した混土貝層・混貝土層が一部ガリー侵食で失われ、それが貝層断面に記録されています。
3 メモ
・これまで崩落物堆積地形の貝層は古く、ガリー侵食地形の貝層は新しいと見立てていましたが、土器出土状況をみるとどうも逆のようです。今後詳しくデータ分析します。
・箱形窪地地形の地学的出自は貝層断面図から侵食と堆積という違いによるり、2つに区分される蓋然性が高まりました。
・第2断面図で混土貝層・混貝土層が侵食されている様子が確認できましたが、純貝層を中心にして充填物の基本は残存しています。混土貝層・混貝土層・純貝層が侵食に強い素材であることが証明されたともいえます。
・北斜面貝層形成は一種の土木事業であると見立てて間違いないという感想を持ちました。