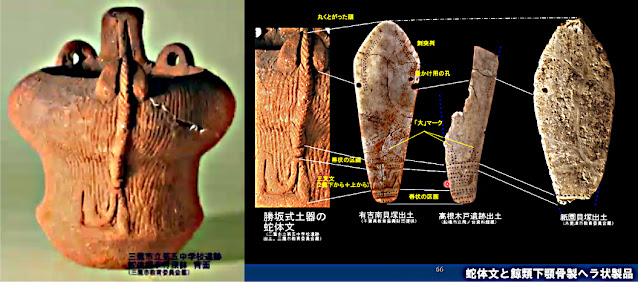Red stereoscopic image from a panoramic point of view
I made a prototype of a red stereoscopic image of a feature seen from a viewpoint. I felt that not only the "from above" viewpoint but also the red stereoscopic image from the viewpoint of the view is useful.
眺望的視点から見た地物の赤色立体画像を試作しました。「上から」の視点だけでなく、眺望的視点の赤色立体画像も有用性があると感じました。
※赤色立体画像は赤色立体原理(千葉達朗先生発明)に基づいて作成された、地物を赤色で立体的に表現する仕組みです。
最近、「動物意匠文付土器平面形状展開モデルの干渉色塗り絵動画」を作りました。
ブログ「花見川流域を歩く番外編」2022.02.16記事「動物意匠文付土器平面形状展開モデルの干渉色塗り絵動画」
動物意匠文付土器平面形状展開モデルの干渉色塗り絵動画
この動画を何回も見ているうちに幾つかの感想が浮かびました。この記事ではその感想に着目して、眺望的視点の赤色立体画像の試作をしてみました。また、最初につくった「上から」みた赤色立体画像を修正しました。
1 干渉色塗り絵動画を見た感想
次のような多様な感想が浮かびました。
ア ある瞬間の干渉色分布は高さの分布を表現しています。その干渉色を位相を変えることで上から下に色を動かしています。この様子をみると、高さ分布の詳細を認識することが容易です。1枚の干渉色分布図はいわば等高線を色塗りした図ですが、これよりも色を動かした方が高さの微妙な分布をはるかに理解しやすくなります。これまで、石器などに干渉色模様を適用して等高線のように表示したことが何回かありましたが、これを動かすと干渉色の価値が高まる可能性があります。
イ この画面は地図のように上から見るのではなく、斜め上から眺望している画面です。このような眺望画面で高さ分布を理解する方が、真上から見るよりも見やすく感じます。
これまで石器や土偶などに干渉色を適用してきましたが、すべて上からでした。これを斜め上から眺望するような画面にすると、干渉色の価値が高まると想定します。
ウ 2つの動物文の間土器表面が盛り上がっていることがよく理解できます。一方、同じ3Dモデルで上から見た赤色立体画像(2022.02.15記事「縄文土器3Dモデルを平面展開してつくる赤色立体画像」)ではこの盛り上がりの表現がないことに気が付きました。2022.02.15赤色立体画像をより正確な画像に作り直す必要があります。
エ これまで作成した赤色立体画像は全て「上から」の画面です。しかし、イの視点から赤色立体画像を斜め上の視点から(眺望的視点から)作成することも意義が大きいのではないかと考えます。
2 「上から」みた赤色立体画像の修正
感想ウにもとづいて、2つの動物文の間の土器表面が盛り上がっている特徴を赤色立体画像で表現出来るように修正しました。
赤色立体画像(修正版)
3 眺望的視点からみた赤色立体画像
眺望的視点からみた赤色立体画像
赤色立体画像は「上から」の画像で作るものであるという先入観がありました。赤色立体地図のイメージが強いからだと思います。しかし、地図的な利用や平面資料としての利用だけでなく、地物の立体性を眺望的視点で表示することも大切であると考えます。そして3Dモデルがあれば眺望的視点で赤色立体画像を作成できるのですから、利用しない手はありません。赤色立体画像を活用する際の選択肢の一つとして眺望的視点で作ることが考えられます。
眺望的視点からみた赤色立体画像(モノトーンテクスチャとの合成)
モノトーンテクスチャと合成すると、テクスチャに照明の明るさ成分がふくまれているため、この場合土器表面のなだらかな起伏を表現する白色部分が消えてしまいます。従って赤色立体画像の良さが失われてしまったとも言えます。正確な実測図などと合成すれば、判りやすい赤色立体画像になると考えます。
眺望的視点からみた赤色立体画像(テクスチャ無し3Dモデルとの合成)
テクスチャ無し3Dモデルと合成すると、表面の照明光反射の明るさにより、土器表面のなだらかな起伏を表現する白色部分が消えてしまっています。