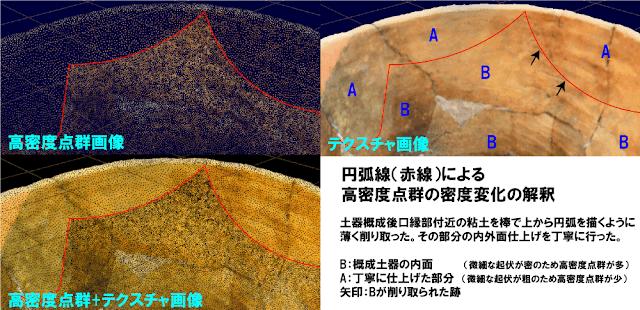縄文社会消長分析学習 47
1 活動目標と期間
下総地域付近の縄文中期から後晩期までを対象に、社会消長を詳しく分析学習して、縄文社会消長の様子とその要因を自分なりに詳しく知る活動を行うことにします。
希少な人生残時間の割り振りの関係から次のような時間消費を予定します。
2020年10月~11月 分析学習テーマを絞り込む活動
2021年1月~2022年12月 テーマを絞り込んだ分析学習
2 分析項目
縄文社会の消長の様子とその要因を生き生きと推察するための分析項目として次のような項目が一般論として考えられます。
・遺物(モノ)の種類、量、質→利用→生業、祭祀
・遺物(モノ)の使用痕、傷、破損→利用
・遺物(モノ)の時系列変化→流行、技術発展
・遺物(モノ)と遺物(モノ)の関係(道具の組み合わせ体系)
・遺物(モノ)と遺構との関係(遺物利用や廃棄場面、遺跡内分布)
・遺構の種類、量、質→生業、交流、人口
・遺構と遺構の関係→遺跡の特性
・遺構の分布
・遺物(モノ)の分布
・遺跡の分布→広域社会
・気温変化(氷床データ等)
・植生変化(花粉分析データ等)
・地形変化(第四紀地形発達史データ等)
このような分析項目のうち、自分の学習目標に効果的であり、またその方法自体に興味が深まるものをいくつか選ぶ作業を最初に行うことにします。
分析項目を無意識的に最初から特定する活動スタートは避けることにします。
3 過去学習の有効活用
この3年間ほどの趣味活動は縄文学習がメインであり、様々な学習活動を行ってきました。これらの学習体験が生きるような学習活動を行うことにします。
下総地域という視点でみれば、これまで次の発掘調査報告書について詳しく学習し、深く分析したものもあります。
・史跡加曽利貝塚発掘調査報告書
・有吉北貝塚発掘調査報告書
・六通貝塚発掘調査報告書
・大膳野南貝塚発掘調査報告書
・西根遺跡発掘調査報告書
・内野第1遺跡発掘調査報告書
また、500以上作成した縄文土器等の3Dモデルも学習データとして活用場面ができればおもしろいことです。
4 学習テーマの渉猟
2021年~2022年に予定している縄文社会消長分析学習の本学習の具体的テーマを2020年10月~12月に絞り込むことにします。
下総縄文社会中期~後晩期の消長を総括的、俯瞰的に知ることは本学習の中で当然行うことですが、それはメインではありません。本学習のメインはかなり絞り込んだテーマ・方法の学習をイメージしています。
その本学習用テーマ・方法を絞り込むために、自分の本当の興味がどこにあるか、そのためのデータ入手や分析技術獲得の可能性について検討したいと思います。
テーマ・方法の渉猟(絞り込み)は3でピックアップした発掘調査報告書を通読・精読する活動を通じて行うことにします。
なお、多数発掘調査報告書の特定データを集成分析する活動が本学習で重要な方法になるに違いないと考えています。
5 学習テーマに関連するかもしれない興味
これまでに興味を持った次のような事象は、学習テーマに関連するかもしれません。
ア 器台と異形台付土器
縄文中期に器台が存在し、後期には出土しません。一方、異形台付土器は中期には存在しませんが、後期には出土します。まるで器台→異形台付土器という交代現象があるように見えます。祭祀の在り方の変化を表現していると想像します。
イ 土偶出土数の後期急増
中期の土偶出土数は大変稀です。一方後期には急増します。祭祀面での変化が観察できます。
ウ 石棒や装身具出土数の後期急増
石棒や装身具の出土数が後期に急増します。土偶と同じで祭祀面での大きな変化が見られます。
エ 加曽利EⅡ式土器のデザイン合理性
加曽利EⅡ式土器は口縁部が平滑なものがほとんどです。前後の時期とくらべて波状口縁部とか把手の存在が少なくなっています。煮沸具としてみると利用上合理的であるように感じることができます。そしてこの時期は人口急増期です。社会の風潮が前後の時期と異なるように感じられます。
オ アリソガイ製ヘラ状貝製品と貝灰
中期有吉北貝塚ではアリソガイ製ヘラ状貝製品が出土します。一方後期遺跡からのヘラ状貝製品出土は少なく、貝灰(漆喰)や骨灰が多量に出土します。アリソガイ製ヘラ状貝製品→貝灰という交代があったかもしれません。
花