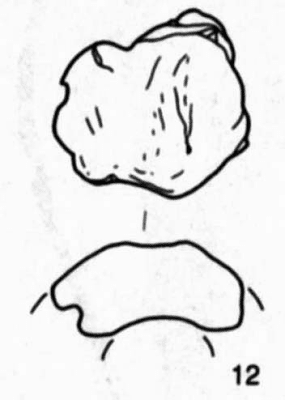貝殻・漆喰、獣骨・焼骨、土器破片の意義の学習が大膳野南貝塚学習、縄文貝塚学習、縄文遺跡学習で特別重要であることにやっと気が付きましたので、忘れないうちにメモしておきます。
1 貝殻・漆喰
貝は毎年採っても翌年にはまた必ず採れる自然の恵みであり、その殻は自然再生の象徴として特別大切なモノ、粗末にできないモノであり、さらに再生の象徴、再生の場にふさわしモノであったのではないかと考えます。
貝殻自体に縄文人は祭祀性を感じていたのだと考えます。
貝殻・漆喰は特別な空間(遺構覆土層や地点貝層、貝層)に残されています。
また純貝層は少なく、多くは加工されています。破砕貝が多く、土と混合され貝の割合が多い場合や少ない場合があります。わざわざ貝殻を破砕して土と捏ね合わせ、その「製品」を使って遺構覆土層や地点貝層、貝層を「建設」しています。漆喰は現代世界からみても正に「製品」で、それで炉や床を「築造」しています。
これらの縄文人の行為はすべて貝殻の持つ再生呪力を期待して行ったのではないかと考えます。
純貝層・混土貝層・混貝土層で遺構を覆土するのは、その底に眠る遺体の再生を願い、あるいはその遺構廃絶(遺構の死)に伴う代替遺構の再生・機能発揮を願っていたのではないかと考えます。
漆喰炉や漆喰貼床は実用的な意味での高機能装置として築造したのではなく、死と再生祭祀の場に相応しい装置として建設・築造されたと考えます。
屋外漆喰炉、屋内漆喰炉、漆喰貼床は実用機能として見るのではなく、そこが祭祀活動の場であったとして見るのが本筋であると考えます。
地点貝層・貝層は廃絶遺構付近空間全体(生活空間全体)を覆うのもですが、それは人々の死と竪穴住居や土坑などの廃絶(死)に対して、それらの再生を願う気持ちから縄文人が行ったものと考えます。
2 獣骨・焼骨
獣も毎年獲っても翌年にはまた必ず獲れる自然の恵みであり、その骨は自然再生の象徴として特別大切なモノ、粗末にできないモノであり、さらに再生の象徴、再生の場にふさわしモノであったのではないかと考えます。
獣骨自体に縄文人は祭祀性を感じていたのだと考えます。
獣骨も貝と同じように特別な空間(遺構覆土層や地点貝層、貝層)に残されています。
これらの獣骨も人や遺構の死と再生に関わる祭祀の重要なアイテムとして活用されたと考えます。
獣骨も砕かれているものがほとんどです。
大膳野南貝塚では鹿頭骨列を除いて動物の骨を儀礼的に扱ったかもしれない事例はありません。砕かれた獣骨は動物自体を対象とした祭祀ではなく、人に関する祭祀に関連した遺物であると考えます。
大膳野南貝塚にはみられませんが、縄文遺跡で一般的にみられる獣骨を焼いて砕いてつくった焼骨は再生呪力が一段と強化されたモノであったと考えます。
3 土器破片
土器は硬く渋く食用に適さない堅果類を美味しい食べ物に変える呪術性を備えた道具です。そのままでは食べられないものを食べられるようにしてくれるという意味で、自然の恵みを享受するために不可欠な道具、生存に不可欠な道具です。
しかし土器はいつかは必ず壊れますから、その時に新しい土器を必ず作ります。
土器は壊れても必ず新しい土器をつくることができます。
つまり土器も貝や獣と同じく、自然の恵みを永続して享受できる象徴であり、再生の象徴でもあったと考えます。
縄文人は不用土器片を貝や獣骨と同じように再生の場の祭祀アイテムにしたと考えます。
用意した不用土器片を祭祀の場でさらに破壊して(細かく割って)、それを死に見立て、その死の裏(反対)にある再生を象徴したのではないかと想像します。
竪穴住居祉でも土坑でも幾つかの破片となった土器片が出土します。これは土器片をその場で割ってそこに撒いたことを示しています。土器片破壊と撒きが送り祭祀(死と再生の祭祀)では重要な活動であったと考えます。
4 学習課題の検討方向
貝、獣骨、土器破片が祭祀の基本アイテムとして使われていたことが判りました。
いずれもそのアイテムを加工する活動が祭祀活動そのものの一部であったと考えられます。
●貝…砕き土と混ぜて撒く、漆喰をつくり撒く・炉や床をつくる
●獣骨…撒く、焼いて砕いて撒く
●土器破片…割って撒く
アイテムを砕き土に返す活動が縄文人の祭祀活動の重要構成要素であり、その最大規模活動が貝塚築造ということになります。
アイテムを加工する活動(砕き土に返す活動)の分類や意味を究明することが今後の学習課題として重要であると考えます。
例
●貝…純貝層・混土貝層・混貝土層の違いの分類とその意味など。発掘調査報告書にくわしい情報があり、分析すれば興味ある結果が得られると感じられます。
●獣骨加工…そもそも出土する獣骨は全て破砕されたものであり、獣食してその結果生まれた生の骨を捨てた(投げた、置いた)ものではないという仮説を立証する必要があります。
獣骨出土は、その遺構の回りで獣食した結果生まれた骨ではなく、過去の獣食で生じた骨を砕いて(加工して)保存しておき、祭祀の際にその空間に撒いたように観察できるように感じられます。そのような観察(発掘調査報告書解読)が正しいか検証する必要があります。
発掘調査報告書の獣骨情報は詳細であり、かつ遺跡全体を悉皆的に調査しているので、詳しく分析すると獣骨加工状況の興味深い状況が浮かび上がる可能性が濃厚です。
●土器破片…発掘調査報告書のスケッチ情報や発掘状況写真から土器片の破壊の仕方が判れば、割って撒く活動の何らかの分類ができ、ひいては祭祀にかかわる有用情報が引き出せるかもしれません。(土器片破壊の方法…投げ込まれてその結果割れた(その後割った)のか、既に割った土器片をバラバラ投げ込んだのか。その違いが判る場合があり、その違いにより祭祀の性格が浮かび上がるかもしれません。)
今朝の花見川風景
この風景空間を散歩しているとき、この記事内容の思考が丸ごと生まれました。
2018年5月20日日曜日
2017年9月17日日曜日
西根遺跡 焼骨出土状況の詳細とその考察
2017.09.16記事「西根遺跡 焼骨はどこで焼かれたか」で焼骨が西根遺跡空間で焼かれて生成され、その場に存置されたことがほぼ判りました。
この記事ではさらに発掘調査報告書掲載情報を詳細に分析して焼骨出土状況を把握・確認するとともに、その事実に基づいた考察を行います。
1 焼骨出土状況の詳細把握
発掘調査報告書の土層断面図記載から骨片が炭化物(焼けた木片)と常に一緒に出土していて、獣骨が西根遺跡空間で焼かれ、その場に存置されたことが明らかになりました。
この様子は発掘調査報告書文章記述では次のよう述べられています。
「集中地点の中には土器のほかに獣骨片や炭化物が多くみられる所もある。獣骨片は比較的小型の哺乳類が中心であり、細かく粉砕され、被熱しているものが大半である。」(16ページ)
「(第1集中地点)3Cグリッドには土器と土器の間に焼けた獣骨片が見られる。
(第2集中地点)包含層内の1部には炭化物や骨片が見られる。
(第3集中地点)小骨片も認められる。」(22ページ)
「獣骨・種子については、調査区の中で目立ったものを採取したものである。分布については、第1集中地点~第5集中地点までは土器の重量分布(第13図)と重なっている。
獣骨(第183図)については、大型片は出土せず、焼けた細片が主体である。全体で1509.6gが出土し、小グリッドで出土大いには、第1集中地点の3C65グリッドで104.2g、第3集中地点の8D76グリッドの197.0g、第4集中地点の9C96グリッド188.0g、10C09グリッドの160.7gであり、いずれも200gを切っており、僅かな出土である。獣骨の種別等については第8章第2節を参照されたい。」(232ページ)
「縄文時代後期の堆積層から採取した遺存体は、いずれも短時間に強い熱を受けたと考えられ、色調は灰白色ないし灰黒色を呈し、変形や損傷が著しい。」(342ページ 理化学的分析)
「西根からは、腐食しにくく、腐肉食性の動物などからの食害を受けにくい遊離歯も回収できないことから、今回の焼骨の中に占める頭骨の頻度はそれほど高くないと見込まれる。」(345ページ 理化学的分析)
「獣骨は、第1集中地点~第5集中地点で検出しているが、どれもほとんど同じ状況で被熱痕が強く残り、イノシシやシカの幼獣の骨片が多いという事実があきらかとなった。これについては今後、他の遺跡との照合が必要である。」(422ページ)
上記の記述から、焼骨の出土は土器が密集するところに分布し、炭化物と骨片が混ざっていて土器と土器の間にみられ、どこも同じような状況であることが確認できます。
2 焼骨づくりに伴う活動の考察
破壊した土器があるその場所で焼骨を作ったことが確認できるのですから、次のような活動を想定できます。
●廃用土器の破壊と焚火による焼骨生成が1回の活動(祭祀)で一緒に行われた。
この活動想定から次のような状況を想像できます。
●廃用土器と生きた幼獣(シカあるいはイノシシ)を持参して西根遺跡に丸木舟で集団がやってくる。
●祭壇(イナウ)を設置し、飾り弓を使ったイオマンテ類似祭祀が行われる。
●獣の頭骨は祭壇に飾り、体部は焼いて集団が食べる。
●残った骨は焼いて骨灰(焼骨)とする。
●焚火の近くで廃用土器を破壊する。
(私はこの活動を堅果類収穫祭の一環であり、印旛浦広域集落群共同の取り組みであり、手賀浦地域との交流の場であり、印旛浦と手賀浦を結ぶミナトの移動(廃絶)ともかかわると考えています。)
このように想像すると次の諸点で発掘情報と整合します。
1 土器片の間に炭化物と焼骨が混ざって出土する。
2 頭骨は祭壇に飾られて放置されるので腐り、土層中に残りにくい。
3 自生する灌木を利用して現場でつくる祭壇(イナウ)は包含土層中に残り、木質(自然木)として出土している。
4 集落から持参した製品としてのイナウは「杭」として出土している。イオマンテ類似祭祀で使った飾り弓は出土。
5 包含層上下の土層から多くの木質が出土していることから、縄文時代後期の戸神川谷津は灌木が豊富であったと考えることができる。従って祭壇(イナウ)づくりはもとより、獣を調理したり焼骨をつくるための焚火の材料には事欠かなかった。
3 焼骨づくりに関する検討項目の考察
焼骨づくりのイメージがより詳しく湧いてきましたので、焼骨づくりの意義に関する検討が新たな項目として抽出されました。
具体的には次の項目について今後検討を深める必要があります。
●動物を調理して食った後の骨を何故焼いて骨灰(焼骨)にしてその場に存置したのか?
土器破壊と骨灰(焼骨)づくり(その存置)は一体の祭祀活動であると考えます。
その祭祀の意味、土器を破壊する意味、骨を焼いて存置する意味について詳しく検討する必要が項目として浮かびあがりました。
具体的には、骨灰(焼骨)存置行為に祭場を白く修飾する風景機能や祭場を固めて破壊土器が動かないようする土木的機能を縄文人が期待していたのかなどについて検討したいと思います。
4 焼骨分布を指標にした検討項目の考察
焼骨と炭化物と土器片が混然一体となって出土する状況は、その場所が後世の流路で破壊されなかったことを物語っています。
仮にその場所が後世の旧流路と平面図上で重なっていても、断面図上では上下に離れていることを物語ります。
つまり、焼骨分布を指標として後世流路により攪乱を受けていない場所を抽出できることになります。
逆に土器が分布し焼骨は分布しない場所で、後世流路と重なる場所は攪乱をうけた場所である可能性が濃厚になります。焼骨や土器の一部が流出してしまったり、上流から土器が水流で運ばれてきた場所になります。
焼骨分布を指標として西根遺跡の詳細地形特性を明らかにすることができます。
今後詳しく空間分析します。
参考 土器分布図(ウススミ)、時代別流路分布図、獣骨分布図(グリッド)のオーバーレイ図 第3~第5集中地点付近
5 参考 感想
1で引用したとおり発掘調査報告書では焼骨について「これについては今後、他の遺跡との照合が必要である。」と述べています。
この記述は、言外に、焼骨に関してはこれ以上検討しないということを述べていると感じました。
発掘調査報告書における「集中地点の性格と意義」における次の結論的記述には焼骨が検討ファクタとしては含まれていないことが推察できます。
「…何を意味するのか具体的には不明である。現代の針供養とも一面では通じるような感を受けるが、穿った見方であろうか。」
土器集中地点の性格と意義を検討するためには破壊土器だけに着目するのではなく、焼骨も重大な検討成分として一緒に検討することが必須だと考えます。
類似他遺跡の検討結果を丹念に見直し、西根遺跡と比較して西根遺跡の意義を考察する必要性が大切であることは論を待ちません。
しかし、その前に西根遺跡内部の徹底した分析・考察が無ければ、類似遺跡情報ばかり集めても、それがどれだけ使えるか何の保証もありません。
この記事ではさらに発掘調査報告書掲載情報を詳細に分析して焼骨出土状況を把握・確認するとともに、その事実に基づいた考察を行います。
1 焼骨出土状況の詳細把握
発掘調査報告書の土層断面図記載から骨片が炭化物(焼けた木片)と常に一緒に出土していて、獣骨が西根遺跡空間で焼かれ、その場に存置されたことが明らかになりました。
この様子は発掘調査報告書文章記述では次のよう述べられています。
「集中地点の中には土器のほかに獣骨片や炭化物が多くみられる所もある。獣骨片は比較的小型の哺乳類が中心であり、細かく粉砕され、被熱しているものが大半である。」(16ページ)
「(第1集中地点)3Cグリッドには土器と土器の間に焼けた獣骨片が見られる。
(第2集中地点)包含層内の1部には炭化物や骨片が見られる。
(第3集中地点)小骨片も認められる。」(22ページ)
「獣骨・種子については、調査区の中で目立ったものを採取したものである。分布については、第1集中地点~第5集中地点までは土器の重量分布(第13図)と重なっている。
獣骨(第183図)については、大型片は出土せず、焼けた細片が主体である。全体で1509.6gが出土し、小グリッドで出土大いには、第1集中地点の3C65グリッドで104.2g、第3集中地点の8D76グリッドの197.0g、第4集中地点の9C96グリッド188.0g、10C09グリッドの160.7gであり、いずれも200gを切っており、僅かな出土である。獣骨の種別等については第8章第2節を参照されたい。」(232ページ)
「縄文時代後期の堆積層から採取した遺存体は、いずれも短時間に強い熱を受けたと考えられ、色調は灰白色ないし灰黒色を呈し、変形や損傷が著しい。」(342ページ 理化学的分析)
「西根からは、腐食しにくく、腐肉食性の動物などからの食害を受けにくい遊離歯も回収できないことから、今回の焼骨の中に占める頭骨の頻度はそれほど高くないと見込まれる。」(345ページ 理化学的分析)
「獣骨は、第1集中地点~第5集中地点で検出しているが、どれもほとんど同じ状況で被熱痕が強く残り、イノシシやシカの幼獣の骨片が多いという事実があきらかとなった。これについては今後、他の遺跡との照合が必要である。」(422ページ)
上記の記述から、焼骨の出土は土器が密集するところに分布し、炭化物と骨片が混ざっていて土器と土器の間にみられ、どこも同じような状況であることが確認できます。
2 焼骨づくりに伴う活動の考察
破壊した土器があるその場所で焼骨を作ったことが確認できるのですから、次のような活動を想定できます。
●廃用土器の破壊と焚火による焼骨生成が1回の活動(祭祀)で一緒に行われた。
この活動想定から次のような状況を想像できます。
●廃用土器と生きた幼獣(シカあるいはイノシシ)を持参して西根遺跡に丸木舟で集団がやってくる。
●祭壇(イナウ)を設置し、飾り弓を使ったイオマンテ類似祭祀が行われる。
●獣の頭骨は祭壇に飾り、体部は焼いて集団が食べる。
●残った骨は焼いて骨灰(焼骨)とする。
●焚火の近くで廃用土器を破壊する。
(私はこの活動を堅果類収穫祭の一環であり、印旛浦広域集落群共同の取り組みであり、手賀浦地域との交流の場であり、印旛浦と手賀浦を結ぶミナトの移動(廃絶)ともかかわると考えています。)
このように想像すると次の諸点で発掘情報と整合します。
1 土器片の間に炭化物と焼骨が混ざって出土する。
2 頭骨は祭壇に飾られて放置されるので腐り、土層中に残りにくい。
3 自生する灌木を利用して現場でつくる祭壇(イナウ)は包含土層中に残り、木質(自然木)として出土している。
4 集落から持参した製品としてのイナウは「杭」として出土している。イオマンテ類似祭祀で使った飾り弓は出土。
5 包含層上下の土層から多くの木質が出土していることから、縄文時代後期の戸神川谷津は灌木が豊富であったと考えることができる。従って祭壇(イナウ)づくりはもとより、獣を調理したり焼骨をつくるための焚火の材料には事欠かなかった。
3 焼骨づくりに関する検討項目の考察
焼骨づくりのイメージがより詳しく湧いてきましたので、焼骨づくりの意義に関する検討が新たな項目として抽出されました。
具体的には次の項目について今後検討を深める必要があります。
●動物を調理して食った後の骨を何故焼いて骨灰(焼骨)にしてその場に存置したのか?
土器破壊と骨灰(焼骨)づくり(その存置)は一体の祭祀活動であると考えます。
その祭祀の意味、土器を破壊する意味、骨を焼いて存置する意味について詳しく検討する必要が項目として浮かびあがりました。
具体的には、骨灰(焼骨)存置行為に祭場を白く修飾する風景機能や祭場を固めて破壊土器が動かないようする土木的機能を縄文人が期待していたのかなどについて検討したいと思います。
4 焼骨分布を指標にした検討項目の考察
焼骨と炭化物と土器片が混然一体となって出土する状況は、その場所が後世の流路で破壊されなかったことを物語っています。
仮にその場所が後世の旧流路と平面図上で重なっていても、断面図上では上下に離れていることを物語ります。
つまり、焼骨分布を指標として後世流路により攪乱を受けていない場所を抽出できることになります。
逆に土器が分布し焼骨は分布しない場所で、後世流路と重なる場所は攪乱をうけた場所である可能性が濃厚になります。焼骨や土器の一部が流出してしまったり、上流から土器が水流で運ばれてきた場所になります。
焼骨分布を指標として西根遺跡の詳細地形特性を明らかにすることができます。
今後詳しく空間分析します。
参考 土器分布図(ウススミ)、時代別流路分布図、獣骨分布図(グリッド)のオーバーレイ図 第3~第5集中地点付近
5 参考 感想
1で引用したとおり発掘調査報告書では焼骨について「これについては今後、他の遺跡との照合が必要である。」と述べています。
この記述は、言外に、焼骨に関してはこれ以上検討しないということを述べていると感じました。
発掘調査報告書における「集中地点の性格と意義」における次の結論的記述には焼骨が検討ファクタとしては含まれていないことが推察できます。
「…何を意味するのか具体的には不明である。現代の針供養とも一面では通じるような感を受けるが、穿った見方であろうか。」
土器集中地点の性格と意義を検討するためには破壊土器だけに着目するのではなく、焼骨も重大な検討成分として一緒に検討することが必須だと考えます。
類似他遺跡の検討結果を丹念に見直し、西根遺跡と比較して西根遺跡の意義を考察する必要性が大切であることは論を待ちません。
しかし、その前に西根遺跡内部の徹底した分析・考察が無ければ、類似遺跡情報ばかり集めても、それがどれだけ使えるか何の保証もありません。
2016年11月16日水曜日
上谷遺跡 竪穴住居敷地内における墨書文字「得」「万」のヒートマップ
被熱ピットが存在していることから小鍛冶遺構であると推定しているA102a竪穴住居について、ミクロな検討を続けています。
この記事では墨書土器文字「得」と「万」の出土分布ヒートマップを作成して、この遺構と集落内集団との関係を考察します。
1 墨書土器文字「得」「万」の集落内における出土領域
上谷遺跡では代表的な墨書文字として「得」「万」「竹」「西」の4つがあげられます。
これまでの検討で、これら4つの代表的墨書文字は居住地を異にする別々の生業集団と対応していると考えてきています。
「得」「万」「竹」「西」を代々伝える4つの集団が上谷遺跡付近集落を構成していたと考えています。
その4つの文字概略分布は次のように図化することができます。
上谷遺跡 代表的墨書文字の出土領域と存被熱ピット竪穴住居
A102a竪穴住居は「得」出土領域と「万」出土領域の中間に位置しています。
またこの付近の存被熱ピット竪穴住居(小鍛冶遺構想定)はほとんどが「得」領域に分布しています。
墨書文字「得」と「万」の出土領域は空間的に棲み分けしていますが、小鍛冶遺構は「得」と「万」二つの集団が合同で運営していたような印象を持つことができる分布になっています。
2 A102a竪穴住居内の「得」「万」分布
A102a竪穴住居 墨書土器「得、万」分布図
この遺構から「得」と「万」の双方が出土していることが一つの特徴です。
同時に「万」は覆土層の上層から出土していて、「得」は「万」より上層に位置していることが読み取れます。
「万」の遺構内持ち込みの後に「得」の持ち込みがあったように観察できます。
3 「得」と「万」のヒートマップ
墨書土器文字「得」と「万」の出土平面位置分布ヒートマップを示します。
上谷遺跡 A102a竪穴住居 墨書土器「得」分布ヒートマップ
上谷遺跡 A102a竪穴住居 墨書土器「万」分布ヒートマップ
得、万ともにその分布は出入り口ピット(西側)付近から竪穴住居に降りて、穴の壁沿いに半周した範囲に多いように観察できます。
竪穴住居中央部に祭壇とか祈祷を行う機能が存在していて、その場所を避けて墨書土器を埋めたと仮想します。
4 A102a竪穴住居から墨書土器文字「得」と「万」が共伴出土する理由
1、2、3から、A102a竪穴住居で墨書土器文字「得」と「万」が共伴出土する理由を次のように空想します。
・小鍛冶機能(鉄器修繕、鉄器流通)は得集団と万集団が共有して所有(運営)していた。その主導権はA102aがその機能を有していた頃は得集団であった。
・小鍛冶機能を有する有力家であるA102a竪穴住居が廃絶したので、その有力家が属する得集団が廃絶跡地の祭祀を行っていた。
・【ケース1】しかし集落全体が衰退する中で「得」集団が衰退して祭祀を行うエネルギーが無くなり、最後の祭祀は「万」集団が代わって挙行した。
・【ケース2】しかし、「得」集団と「万」集団の力関係が変化して、A102a竪穴住居付近が全て「万」集団の支配域となり、最後の祭祀開催権を「万」集団が「得」集団から奪った。
この記事では墨書土器文字「得」と「万」の出土分布ヒートマップを作成して、この遺構と集落内集団との関係を考察します。
1 墨書土器文字「得」「万」の集落内における出土領域
上谷遺跡では代表的な墨書文字として「得」「万」「竹」「西」の4つがあげられます。
これまでの検討で、これら4つの代表的墨書文字は居住地を異にする別々の生業集団と対応していると考えてきています。
「得」「万」「竹」「西」を代々伝える4つの集団が上谷遺跡付近集落を構成していたと考えています。
その4つの文字概略分布は次のように図化することができます。
上谷遺跡 代表的墨書文字の出土領域と存被熱ピット竪穴住居
A102a竪穴住居は「得」出土領域と「万」出土領域の中間に位置しています。
またこの付近の存被熱ピット竪穴住居(小鍛冶遺構想定)はほとんどが「得」領域に分布しています。
墨書文字「得」と「万」の出土領域は空間的に棲み分けしていますが、小鍛冶遺構は「得」と「万」二つの集団が合同で運営していたような印象を持つことができる分布になっています。
2 A102a竪穴住居内の「得」「万」分布
A102a竪穴住居 墨書土器「得、万」分布図
この遺構から「得」と「万」の双方が出土していることが一つの特徴です。
同時に「万」は覆土層の上層から出土していて、「得」は「万」より上層に位置していることが読み取れます。
「万」の遺構内持ち込みの後に「得」の持ち込みがあったように観察できます。
3 「得」と「万」のヒートマップ
墨書土器文字「得」と「万」の出土平面位置分布ヒートマップを示します。
上谷遺跡 A102a竪穴住居 墨書土器「得」分布ヒートマップ
上谷遺跡 A102a竪穴住居 墨書土器「万」分布ヒートマップ
得、万ともにその分布は出入り口ピット(西側)付近から竪穴住居に降りて、穴の壁沿いに半周した範囲に多いように観察できます。
竪穴住居中央部に祭壇とか祈祷を行う機能が存在していて、その場所を避けて墨書土器を埋めたと仮想します。
4 A102a竪穴住居から墨書土器文字「得」と「万」が共伴出土する理由
1、2、3から、A102a竪穴住居で墨書土器文字「得」と「万」が共伴出土する理由を次のように空想します。
・小鍛冶機能(鉄器修繕、鉄器流通)は得集団と万集団が共有して所有(運営)していた。その主導権はA102aがその機能を有していた頃は得集団であった。
・小鍛冶機能を有する有力家であるA102a竪穴住居が廃絶したので、その有力家が属する得集団が廃絶跡地の祭祀を行っていた。
・【ケース1】しかし集落全体が衰退する中で「得」集団が衰退して祭祀を行うエネルギーが無くなり、最後の祭祀は「万」集団が代わって挙行した。
・【ケース2】しかし、「得」集団と「万」集団の力関係が変化して、A102a竪穴住居付近が全て「万」集団の支配域となり、最後の祭祀開催権を「万」集団が「得」集団から奪った。
2016年10月22日土曜日
上谷遺跡 鞴羽口出土竪穴住居(遺物多出土遺構)
上谷遺跡の鍛冶関連遺物出土遺構の検討(学習)を継続しています。
この記事では遺物多出土遺構であるA233竪穴住居について検討します。
1 A233竪穴住居の位置
A233竪穴住居の位置
A233竪穴住居はこの遺跡の「西」側の掘立柱建物群の中央部付近に位置しています。
2 A233竪穴住居の特徴と出土物
A233竪穴住居は竈の改替を行っています。
A233
A233竪穴住居は建物の主要施設の竈の改替を行っている、つまり建物の改築を行っているのですから、その情報から、この住居に居住していた家族は集落の中で裕福であり、恐らく支配層、リーダー層に位置する家族であったと想像します。
A233竪穴住居からの出土物は極めて多く、墨書土器も多数出土しています。
A233
A233
A233
A233竪穴住居の住人が集落の支配層、リーダー層クラスであったという想定と、A233竪穴住居廃絶後にその遺構を覆った堆積層(覆土層)に多数の遺物が含まれていることは強く関連する事象として捉えることができると考えます。
つまり、A233竪穴住居の住人が集落の中で重要な役割を果たした人物であることから、その人物が死亡して家長が途絶えてその住居を廃絶した後、その住居跡空間(窪地)がその人物やその人物が果たした機能を弔い、あるいは感謝するなどの祭祀の場になったと想定します。
A233竪穴住居廃絶後、その空間を通じて思い起こすことができることを共通心理として人々の祭祀が行われたと想定します。
その祭祀の際に、お供え物として各種鉄器や墨書土器が置かれた、埋められた、投げられたのだと思います。
「西」と墨書された土器の文字「西」が残るように土器を割って、それを供えた(置いた、埋めた、投げた)祭祀が行われたと考えます 。
ですから、文字「西」を共有する集団と関わる人物、恐らく「西」集団のリーダー格の人物がA233竪穴住居の家長であったと考えます。
このような状況の中で、鞴羽口出土を考える必要があります。
3 鞴羽口出土状況と解釈(想像)
鞴羽口の記載は次のようになっています。
長(76)×径-×厚32、依存度が小さく、内径は復元できず、淡褐色、普、砂質、断片
鞴羽口
鞴羽口の出土層位は床面あるいは床面に近接する覆土層のように読み取ることができます。
鞴羽口の出土位置
2の考察を踏まえ、A233鞴羽口出土を次のように解釈(想像)します。
・A233竪穴住居には墨書文字「西」を共有する生業集団のリーダー格人物が住んでいた。
・そのリーダー格人物が死んで家長が途絶えたため、住居を廃絶(取り壊し)した。
・住居廃絶空間はすぐに覆土して平地利用空間に戻すのではなく、穴として残して祭祀的空間として一定期間利用できるようにした。
・住居廃絶時に鞴羽口破片が床面に置かれた。あるいは廃絶後の祭祀の際に鞴羽口破片が置かれた。
・鞴羽口破片が置かれたのは、A233に住んでいた「西」集団リーダー格人物が鍛冶業務にも何らかの形で関わっていたからであると想像します。
・出土物に鉄製品が多いことと鞴羽口出土が関連していると捉えると、「西」集団の各種鉄製品の補修やリサイクルを行う鍛冶業務を、この死んだリーダー格人物が統括、支配していたと想定できます。
・出土鉄製品には刀子、鏃が多いことから、死んだリーダー格人物は治安や防衛にも関わっていたと考えることができます。従ってその格(位)はかなり上であったと考えることができます。
なお、覆土層の各細層記述には各所に焼土粒混入が含まれています。
この記述からA133竪穴住居跡(穴)で行われた祭祀では火が使われた可能性が濃厚です。
また、打ち欠きして「西」がよく見えるようにした土器片や鉄製品等を供えた祭祀は、死んだリーダー格人物の記憶が人々に残っている期間、繰り返しておこなわれたと考えます。
現代の1回忌、3回忌、7回忌、13回忌みたいな心性で、A133竪穴住居跡(穴)空間が祭祀の場になったと空想します。
なお、墓ではない家跡という空間が祭祀の場になっていたという自分の仮説に、自分自身が大いに興味を持っています。
空間(場所)に対して、共通の記憶をたよりにして、人々が強い意味を与える事象として興味を抱きます。
リーダー格でない一般住民が居住した竪穴住居を廃絶する場合、その場所を生活空間として別利用するために即座に埋め立てする場合もあったと考えます。
2016.09.12記事「上谷遺跡 一気埋戻し竪穴住居が馬歩行空間を示す」参照
この記事では遺物多出土遺構であるA233竪穴住居について検討します。
1 A233竪穴住居の位置
A233竪穴住居の位置
A233竪穴住居はこの遺跡の「西」側の掘立柱建物群の中央部付近に位置しています。
2 A233竪穴住居の特徴と出土物
A233竪穴住居は竈の改替を行っています。
A233
A233竪穴住居は建物の主要施設の竈の改替を行っている、つまり建物の改築を行っているのですから、その情報から、この住居に居住していた家族は集落の中で裕福であり、恐らく支配層、リーダー層に位置する家族であったと想像します。
A233竪穴住居からの出土物は極めて多く、墨書土器も多数出土しています。
A233
A233
A233
A233竪穴住居の住人が集落の支配層、リーダー層クラスであったという想定と、A233竪穴住居廃絶後にその遺構を覆った堆積層(覆土層)に多数の遺物が含まれていることは強く関連する事象として捉えることができると考えます。
つまり、A233竪穴住居の住人が集落の中で重要な役割を果たした人物であることから、その人物が死亡して家長が途絶えてその住居を廃絶した後、その住居跡空間(窪地)がその人物やその人物が果たした機能を弔い、あるいは感謝するなどの祭祀の場になったと想定します。
A233竪穴住居廃絶後、その空間を通じて思い起こすことができることを共通心理として人々の祭祀が行われたと想定します。
その祭祀の際に、お供え物として各種鉄器や墨書土器が置かれた、埋められた、投げられたのだと思います。
「西」と墨書された土器の文字「西」が残るように土器を割って、それを供えた(置いた、埋めた、投げた)祭祀が行われたと考えます 。
ですから、文字「西」を共有する集団と関わる人物、恐らく「西」集団のリーダー格の人物がA233竪穴住居の家長であったと考えます。
このような状況の中で、鞴羽口出土を考える必要があります。
3 鞴羽口出土状況と解釈(想像)
鞴羽口の記載は次のようになっています。
長(76)×径-×厚32、依存度が小さく、内径は復元できず、淡褐色、普、砂質、断片
鞴羽口
鞴羽口の出土層位は床面あるいは床面に近接する覆土層のように読み取ることができます。
鞴羽口の出土位置
2の考察を踏まえ、A233鞴羽口出土を次のように解釈(想像)します。
・A233竪穴住居には墨書文字「西」を共有する生業集団のリーダー格人物が住んでいた。
・そのリーダー格人物が死んで家長が途絶えたため、住居を廃絶(取り壊し)した。
・住居廃絶空間はすぐに覆土して平地利用空間に戻すのではなく、穴として残して祭祀的空間として一定期間利用できるようにした。
・住居廃絶時に鞴羽口破片が床面に置かれた。あるいは廃絶後の祭祀の際に鞴羽口破片が置かれた。
・鞴羽口破片が置かれたのは、A233に住んでいた「西」集団リーダー格人物が鍛冶業務にも何らかの形で関わっていたからであると想像します。
・出土物に鉄製品が多いことと鞴羽口出土が関連していると捉えると、「西」集団の各種鉄製品の補修やリサイクルを行う鍛冶業務を、この死んだリーダー格人物が統括、支配していたと想定できます。
・出土鉄製品には刀子、鏃が多いことから、死んだリーダー格人物は治安や防衛にも関わっていたと考えることができます。従ってその格(位)はかなり上であったと考えることができます。
なお、覆土層の各細層記述には各所に焼土粒混入が含まれています。
この記述からA133竪穴住居跡(穴)で行われた祭祀では火が使われた可能性が濃厚です。
また、打ち欠きして「西」がよく見えるようにした土器片や鉄製品等を供えた祭祀は、死んだリーダー格人物の記憶が人々に残っている期間、繰り返しておこなわれたと考えます。
現代の1回忌、3回忌、7回忌、13回忌みたいな心性で、A133竪穴住居跡(穴)空間が祭祀の場になったと空想します。
なお、墓ではない家跡という空間が祭祀の場になっていたという自分の仮説に、自分自身が大いに興味を持っています。
空間(場所)に対して、共通の記憶をたよりにして、人々が強い意味を与える事象として興味を抱きます。
リーダー格でない一般住民が居住した竪穴住居を廃絶する場合、その場所を生活空間として別利用するために即座に埋め立てする場合もあったと考えます。
2016.09.12記事「上谷遺跡 一気埋戻し竪穴住居が馬歩行空間を示す」参照
2016年10月10日月曜日
上谷遺跡 鞴羽口出土A102a竪穴住居の検討
鞴羽口や鉄滓が出土した遺構について、発掘調査報告書の記載を詳しく検討し、想像も交えて学習します。
この記事ではA102a竪穴住居について検討します。
1 A102a竪穴住居の位置
A102a竪穴住居の位置
2 A102a竪穴住居の特徴
次にA102a竪穴住居の特徴を列挙します。(発掘調査報告書から引用、表は作成。)
● A102aとA102bの重複
A102a竪穴住居はA102b竪穴住居と重複している。
A102aが新しい遺構、A102bは現状からみた推定規模は大きくなるが、堀込が浅く、床面も捉えきれなかった遺構である。A102aとの重複関係や規模等から竪穴住居跡としてが、竪穴状遺構と捉えた方がよいかもしれない。
● 規模のやや大きな竪穴住居
A102aは長軸5.62m×短軸5.57m×壁高0.83m、主軸方向はN-75°-Eを示す。竈を再構築している。
● 炉状ピットの検出
住居跡中央に炉のような浅いピットが検出されているが、住居廃絶後の燃焼行為の結果ではないと覆土から捉えられ、本住居跡に伴う炉状のピットであった。
ピット覆土は、焼土を混入した褐色土が1~5cmの厚さで堆積していた。
貼床を剥がしたような凹凸のあるハードローム面を坑底として、火床範囲と捉えたものも赤味を帯びる程度であった。
調査では、本ピットに係るような付帯遺構は検出できなかった。
覆土は基本的には自然堆積であり、色調や包含物により分層した。
A102a・b
● 極めて多数の遺物出土
A102aの出土遺物は極めて多く破片数は3000点を超えるものであったが、A102bの遺物の出土は少なかった。
3000点を超える遺物点数のため、全体的な平面及び垂直分布状況も、全域から出土しているものとなっている。
しかし、掲載した遺物は床面出土よりも覆土中層の遺物が多く、自然堆積によって住居跡が埋没する過程で、遺物の廃棄が行われたことを示している。
A102a・A102b出土遺物分布図
A102a・A102b出土遺物 1
A102a・A102b出土遺物 2
A102a・A102b出土遺物 3
● 墨書土器の出土が多い
特に墨書土器の出土が多く、87点に及んでいる。
記された文字は「得」が最も多く、31点が出土している。
また、「万」「大万」「仁」等も出土しており、Ⅱ地区の特徴的な文字の両者を出土する竪穴住居跡である。
A102a竪穴住居 墨書土器
● 鉄器出土が多い
この他には鉄器の出土も多く、鉄鏃3点、刀子3点、紡錘車2点等の12点を数える。
紡錘車は石製も出土している。
A102a竪穴住居 遺物観察表の集計
● 鞴羽口の出土
鞴の羽口片も出土しており、本住居跡ではその明瞭な形跡は認められなかったが、上谷遺跡における小鍛冶生産を想定できる資料といえよう。
A102a竪穴住居 鞴羽口
現存高(4.80)、内面 高温のため灰色化、羽口部分。
3 検討(想像を交えた学習)
3-1 炉状ピットの意義
竪穴住居の中にその住居に由来する炉状ピットがあるのですから、それが小鍛冶施設であったと考えることが合理的です。
ただし簡易な小鍛冶であり、炉の構造が残らなかったのだと考えます。
参考 古代の鍛冶工房復元図
「千葉県の歴史 資料編考古4(遺跡・遺構・遺物)」(千葉県発行)から引用
炉状ピットは既成鉄製品の修理やリサイクルなどのための簡易な鍛冶跡と考えます。
3-2 鞴羽口出土の意味
発掘調査報告書掲載図を拡大すると次のようになり、鞴羽口出土は覆土層の中層からであることがわかります。
A102a竪穴住居 鞴羽口出土位置
覆土層の中層から出土した鞴羽口片はこの竪穴住居で使われたものではない可能性が高いと考えます。
この住居で使われ鞴羽口が一度住居外に持ち出され、後に再度持ち込まれたと考えることの可能性もゼロではないと思いますが、その可能性は低いと考えます。
小鍛冶が行われた竪穴住居の覆土層に、別の場所で使われた鞴羽口が持ち込まれたということになります。
それは全くの偶然ということではなく、一定の必然性があると考えられますの、その考えを次にメモしておきます。
●メモ1 小鍛冶技術者(=集団指導者)に対する弔い
小鍛冶が行われていて廃絶したA102a竪穴住居は比較的大きな竪穴住居であり、また掘立柱建物群の入り口付近という集団拠点の要衝に位置しています。
このことから、A102a竪穴住居住人は集団の指導層に属していたと想定できます。
従って、小鍛冶という集団にとって重要な技術を有し、かつ指導者であるものが死亡して、その住居が廃絶したとき、集団住民がその廃絶した住居を、そこは決して墓ではありませんが、一種の弔いの場として、小鍛冶に関連する物品を供えたと考えます。
現代でも人が死ぬと1周忌、3回忌、7回忌などがありますが、同じような心性で、墓ではないが、過去に小鍛冶という重要な機能を担った人に感謝し、弔う気持ちから、お参り(祭祀)があり、その時関連する物が置かれたと考えます。
その時鞴羽口破片が供えられた(置かれた)と考えます。
●メモ2 A102a竪穴住居空間(場所)が過去に有した小鍛冶という有用機能に対する感謝の念
A102a竪穴住居で小鍛冶が行われ集団にとって大変有用な機能を有していた時期があり、その有用な機能が廃絶したとき、その空間の有用であった機能に感謝する気持ちから、小鍛冶に関連する物品を供えた、置いた、埋めたと考えます。
別の場所の小鍛冶で鞴羽口が壊れた時、その破片をわざわざA102a竪穴住居跡の穴にお供え物として持ってきたというようなことも想定します。
メモ1とメモ2は類似していますから通底していることは確かです。
私は、墓ではない場所に祭祀的なことが感じられるので、メモ2が大切な視点であり、その視点は現代社会ではほとんど失われていると考えます。
空間(場所)そのものに対する「思い」を古代人は持っていて、現代人はその感覚がすっかり退化していると考えます。
メモ2の視点に立脚すると多くの遺構・遺物の意味が解読できるような気がしています。
3-3 鉄器多数出土の意味
鞴羽口出土と同じ意味であると考えます。
つまり小鍛冶技術者(=集団指導者)に対する弔い、あるいはその場所の過去の小鍛冶機能に対する感謝の念からだと考えます。
恐らく、壊れたあるいは不用になった鉄器をその場にお供えした(あるいは埋めた)弔いや感謝の祭祀があったのだと思います。
3-4 墨書土器多数出土の意味
鞴羽口出土や鉄器多数出土の意味と共通すると思います。
鞴羽口や鉄器をお供えする祭祀の際に、集団のエンブレムとなっている文字「得」が墨書された土器を持ちより、酒宴をおこない、最後にそれを打ち欠いてその場に供えた(埋めた、投げた)のだと思います。
この記事ではA102a竪穴住居について検討します。
1 A102a竪穴住居の位置
A102a竪穴住居の位置
墨書文字「得」が多出する集団と関わる掘立柱建物群の近く(入口?)にA102a竪穴住居は存在します。
その位置からA102a竪穴住居は集団の中で重要な機能を有していたと考えても不合理なことはありません。
2 A102a竪穴住居の特徴
次にA102a竪穴住居の特徴を列挙します。(発掘調査報告書から引用、表は作成。)
● A102aとA102bの重複
A102a竪穴住居はA102b竪穴住居と重複している。
A102aが新しい遺構、A102bは現状からみた推定規模は大きくなるが、堀込が浅く、床面も捉えきれなかった遺構である。A102aとの重複関係や規模等から竪穴住居跡としてが、竪穴状遺構と捉えた方がよいかもしれない。
● 規模のやや大きな竪穴住居
A102aは長軸5.62m×短軸5.57m×壁高0.83m、主軸方向はN-75°-Eを示す。竈を再構築している。
● 炉状ピットの検出
住居跡中央に炉のような浅いピットが検出されているが、住居廃絶後の燃焼行為の結果ではないと覆土から捉えられ、本住居跡に伴う炉状のピットであった。
ピット覆土は、焼土を混入した褐色土が1~5cmの厚さで堆積していた。
貼床を剥がしたような凹凸のあるハードローム面を坑底として、火床範囲と捉えたものも赤味を帯びる程度であった。
調査では、本ピットに係るような付帯遺構は検出できなかった。
覆土は基本的には自然堆積であり、色調や包含物により分層した。
A102a・b
● 極めて多数の遺物出土
A102aの出土遺物は極めて多く破片数は3000点を超えるものであったが、A102bの遺物の出土は少なかった。
3000点を超える遺物点数のため、全体的な平面及び垂直分布状況も、全域から出土しているものとなっている。
しかし、掲載した遺物は床面出土よりも覆土中層の遺物が多く、自然堆積によって住居跡が埋没する過程で、遺物の廃棄が行われたことを示している。
A102a・A102b出土遺物分布図
A102a・A102b出土遺物 1
A102a・A102b出土遺物 2
A102a・A102b出土遺物 3
● 墨書土器の出土が多い
特に墨書土器の出土が多く、87点に及んでいる。
記された文字は「得」が最も多く、31点が出土している。
また、「万」「大万」「仁」等も出土しており、Ⅱ地区の特徴的な文字の両者を出土する竪穴住居跡である。
A102a竪穴住居 墨書土器
● 鉄器出土が多い
この他には鉄器の出土も多く、鉄鏃3点、刀子3点、紡錘車2点等の12点を数える。
紡錘車は石製も出土している。
A102a竪穴住居 遺物観察表の集計
● 鞴羽口の出土
鞴の羽口片も出土しており、本住居跡ではその明瞭な形跡は認められなかったが、上谷遺跡における小鍛冶生産を想定できる資料といえよう。
A102a竪穴住居 鞴羽口
現存高(4.80)、内面 高温のため灰色化、羽口部分。
3 検討(想像を交えた学習)
3-1 炉状ピットの意義
竪穴住居の中にその住居に由来する炉状ピットがあるのですから、それが小鍛冶施設であったと考えることが合理的です。
ただし簡易な小鍛冶であり、炉の構造が残らなかったのだと考えます。
参考 古代の鍛冶工房復元図
「千葉県の歴史 資料編考古4(遺跡・遺構・遺物)」(千葉県発行)から引用
炉状ピットは既成鉄製品の修理やリサイクルなどのための簡易な鍛冶跡と考えます。
3-2 鞴羽口出土の意味
発掘調査報告書掲載図を拡大すると次のようになり、鞴羽口出土は覆土層の中層からであることがわかります。
A102a竪穴住居 鞴羽口出土位置
覆土層の中層から出土した鞴羽口片はこの竪穴住居で使われたものではない可能性が高いと考えます。
この住居で使われ鞴羽口が一度住居外に持ち出され、後に再度持ち込まれたと考えることの可能性もゼロではないと思いますが、その可能性は低いと考えます。
それは全くの偶然ということではなく、一定の必然性があると考えられますの、その考えを次にメモしておきます。
●メモ1 小鍛冶技術者(=集団指導者)に対する弔い
小鍛冶が行われていて廃絶したA102a竪穴住居は比較的大きな竪穴住居であり、また掘立柱建物群の入り口付近という集団拠点の要衝に位置しています。
このことから、A102a竪穴住居住人は集団の指導層に属していたと想定できます。
従って、小鍛冶という集団にとって重要な技術を有し、かつ指導者であるものが死亡して、その住居が廃絶したとき、集団住民がその廃絶した住居を、そこは決して墓ではありませんが、一種の弔いの場として、小鍛冶に関連する物品を供えたと考えます。
現代でも人が死ぬと1周忌、3回忌、7回忌などがありますが、同じような心性で、墓ではないが、過去に小鍛冶という重要な機能を担った人に感謝し、弔う気持ちから、お参り(祭祀)があり、その時関連する物が置かれたと考えます。
その時鞴羽口破片が供えられた(置かれた)と考えます。
●メモ2 A102a竪穴住居空間(場所)が過去に有した小鍛冶という有用機能に対する感謝の念
メモ1とメモ2は類似していますから通底していることは確かです。
私は、墓ではない場所に祭祀的なことが感じられるので、メモ2が大切な視点であり、その視点は現代社会ではほとんど失われていると考えます。
空間(場所)そのものに対する「思い」を古代人は持っていて、現代人はその感覚がすっかり退化していると考えます。
メモ2の視点に立脚すると多くの遺構・遺物の意味が解読できるような気がしています。
3-3 鉄器多数出土の意味
鞴羽口出土と同じ意味であると考えます。
つまり小鍛冶技術者(=集団指導者)に対する弔い、あるいはその場所の過去の小鍛冶機能に対する感謝の念からだと考えます。
恐らく、壊れたあるいは不用になった鉄器をその場にお供えした(あるいは埋めた)弔いや感謝の祭祀があったのだと思います。
3-4 墨書土器多数出土の意味
鞴羽口出土や鉄器多数出土の意味と共通すると思います。
鞴羽口や鉄器をお供えする祭祀の際に、集団のエンブレムとなっている文字「得」が墨書された土器を持ちより、酒宴をおこない、最後にそれを打ち欠いてその場に供えた(埋めた、投げた)のだと思います。
登録:
投稿 (Atom)