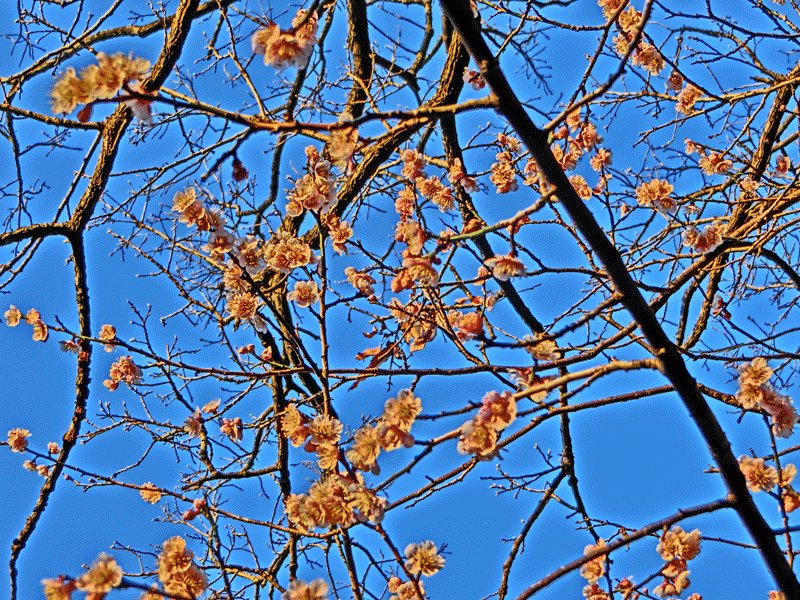気温が高く、惰性で着こんだ防寒着がうっとうしくなる気分です。
コジュケイの高い叫び声とウグイスの声の双方が絶えません。
雨上がりで風景の雰囲気がいつもと違います。
東の空
東の空
ちぎれ雲と月が風景を絵にしています。
花見川 横戸緑地下付近
弁天橋
弁天橋から下流
弁天橋から上流
弁天橋
2015年3月10日火曜日
2015年3月9日月曜日
直道遺跡と居寒台遺跡の位置と概要
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.81 直道遺跡と居寒台遺跡の位置と概要
上ノ台遺跡の発掘調査報告書は大冊全6巻で体系的にとりまとめられていましたから、利用する方にとっては便利でした。
花見川河口拠点集落の遺跡である直道遺跡と居寒台遺跡の発掘調査報告書は全部で21冊にわかれていて、重複等もあり、内容理解の前に、報告書と遺跡調査区を対応させるという形式的把握が一大仕事です。
何とか形式的把握ができましたので、そこまでをまとめてみます。
1 直道遺跡と居寒台遺跡の位置
直道遺跡と居寒台遺跡の位置を地図で表すと次のようになります。
直道遺跡・居寒台遺跡の位置
居寒台遺跡の調査は昭和55年にスタートし、その後順次調査区を増やし、平成19年度報告書までの間に、いつの間にか直道遺跡を取り囲むような様相を呈しています。
この図に描かれているくくり線は居寒台遺跡の発掘調査報告書に描かれているもので、拠点集落が台地全体に拡がっている様相のイメージです。
2 直道遺跡と居寒台遺跡の概要
概要を知るために、遺跡調査区別に検出された竪穴住居址軒数と掘立柱建物址棟数をまとめてみました。
直道遺跡と居寒台遺跡の調査区
直道遺跡・居寒台遺跡で検出された古墳・奈良・平安時代の竪穴住居址及び掘立柱建物址の数
拠点集落が台地全体に拡がっているイメージのくくり線の内部(約15.6h)で、実際に発掘された面積は約13.5%ですから、この拠点集落の規模は上ノ台遺跡をはるかに上回る大きな規模であることは確かです。
特に掘立柱建物址の数が多く、単なる居住地ではなく、国家的意義のある軍事拠点・交通拠点であったことを物語っています。
上ノ台遺跡の発掘調査報告書は大冊全6巻で体系的にとりまとめられていましたから、利用する方にとっては便利でした。
花見川河口拠点集落の遺跡である直道遺跡と居寒台遺跡の発掘調査報告書は全部で21冊にわかれていて、重複等もあり、内容理解の前に、報告書と遺跡調査区を対応させるという形式的把握が一大仕事です。
何とか形式的把握ができましたので、そこまでをまとめてみます。
1 直道遺跡と居寒台遺跡の位置
直道遺跡と居寒台遺跡の位置を地図で表すと次のようになります。
直道遺跡・居寒台遺跡の位置
居寒台遺跡の調査は昭和55年にスタートし、その後順次調査区を増やし、平成19年度報告書までの間に、いつの間にか直道遺跡を取り囲むような様相を呈しています。
この図に描かれているくくり線は居寒台遺跡の発掘調査報告書に描かれているもので、拠点集落が台地全体に拡がっている様相のイメージです。
2 直道遺跡と居寒台遺跡の概要
概要を知るために、遺跡調査区別に検出された竪穴住居址軒数と掘立柱建物址棟数をまとめてみました。
直道遺跡と居寒台遺跡の調査区
直道遺跡・居寒台遺跡で検出された古墳・奈良・平安時代の竪穴住居址及び掘立柱建物址の数
拠点集落が台地全体に拡がっているイメージのくくり線の内部(約15.6h)で、実際に発掘された面積は約13.5%ですから、この拠点集落の規模は上ノ台遺跡をはるかに上回る大きな規模であることは確かです。
特に掘立柱建物址の数が多く、単なる居住地ではなく、国家的意義のある軍事拠点・交通拠点であったことを物語っています。
2015年3月8日日曜日
花見川河口の古代住居址から馬骨出土の事実を知る
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.80 花見川河口の古代住居址から馬骨出土の事実を知る
上ノ台遺跡の検討を一旦打ち切り、幕張の砂丘(の乗る砂州)・花見川を挟んで上ノ台遺跡と向かい合う検見川台地上の直道遺跡・居寒台遺跡の検討をします。
直道遺跡・居寒台遺跡は一連の古代拠点集落の別の場所を指していると考えられています。この花見川河口拠点集落は「古墳時代後期~末期」-「奈良時代」-「平安時代」と時代の連続性が確認され、多数の掘立建物が検出されています。
古墳時代の拠点集落上ノ台遺跡が終焉し、奈良・平安時代に新拠点集落直道・居寒台遺跡が勃興したとイメージできます。
直道遺跡・居寒台遺跡の位置
(基図は迅速図、明治前期測量)
直道遺跡・居寒台遺跡を検討するために、千葉市立図書館WEBサイトで関連する発掘調査報告書等を検索すると全部で21件ヒットしました。その内主要なものを全て含む20件の資料の情報を入手しましたので、これから検討して行きます。
この記事では直道遺跡の住居址から馬骨が出土しているという事実を知りましたので、メモしておきます。
直道遺跡における馬骨出土の状況
「千葉市直道遺跡」(1995、財団法人千葉市文化財調査協会)から引用
説明
「この住居址で特筆すべき点は馬の骨が検出されたことである。骨の検出状況は、カマド付近を中心に住居の中央部に分布している。打ち割られたものが多く、部位がバラバラになっており、床面に密着しているもの、柱穴に落ち込んでいるもの、カマドを構築している砂質粘土の中から検出されたものなどがあり、住居を使わなくなって間もない時期に骨が残されたことを示している。また、床面の近くには焼土と灰の層があり、火熱を受けて炭化しているものも多かった。こうしたことから、食用にしたその残滓をこの住居跡に廃棄したものと考えられる。住居跡の覆土中にロームブロックを多く含む層があり、人為的に埋め戻している可能性がある。」「千葉市直道遺跡」(1995、財団法人千葉市文化財調査協会)
廃滅直後の住居址近くで人が馬を食し、その残滓をこの住居址に捨て、近くの土でその上を覆ったという状況のようです。
この付近は玄蕃所(俘囚収容所)があり軍事色が強い場所であったと考えてきています(※)が、馬骨が出土したことにより、検見川台地上で馬が使われていたことが証明されます。
この時代の馬は軍事を象徴する家畜ですから、馬骨出土は遺跡に想定される軍事的機能を傍証します。
具体的には、直道・居寒台遺跡が指す検見川台地拠点集落は単なる生活のための集落ではなく、公的軍事的機能を有する集団が居住する集落であることを傍証することになります。
※
2014.12.24記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」参照
2014.12.24記事「花見川河口津付近の遺跡と地名」参照
……………………………………………………………………
動物遺体はリスト化されない不思議
上ノ台遺跡の住居址で牛骨出土があり、直道遺跡の住居址でも馬骨出土がありました。
何れの発掘調査報告書でも出土遺物は住居址単位に説明し、微細なものまで洩れなく住居址毎にリスト化しています。
その遺物リストには牛骨も馬骨も掲載されません。出土状況から牛骨や馬骨が「遺物」ではないと判断したからだと思います。
しかし、牛骨や馬骨が重要な考古資料であることは間違いありません。遺物リストに入れられないなら、別の出土物リストとか、考古資料リストなどをつくって掲載すればわかりやすくなります。
上ノ台遺跡の牛骨も、直道遺跡の馬骨もリスト化されていないために、結局のところ遺跡の状況を要約するときには漏れてしまっています。
そのために、その情報が重要であるにもかかわらず、報告書を事細かに調べる人以外には伝わらないことになります。
上ノ台遺跡の検討を一旦打ち切り、幕張の砂丘(の乗る砂州)・花見川を挟んで上ノ台遺跡と向かい合う検見川台地上の直道遺跡・居寒台遺跡の検討をします。
直道遺跡・居寒台遺跡は一連の古代拠点集落の別の場所を指していると考えられています。この花見川河口拠点集落は「古墳時代後期~末期」-「奈良時代」-「平安時代」と時代の連続性が確認され、多数の掘立建物が検出されています。
古墳時代の拠点集落上ノ台遺跡が終焉し、奈良・平安時代に新拠点集落直道・居寒台遺跡が勃興したとイメージできます。
直道遺跡・居寒台遺跡の位置
(基図は迅速図、明治前期測量)
直道遺跡・居寒台遺跡を検討するために、千葉市立図書館WEBサイトで関連する発掘調査報告書等を検索すると全部で21件ヒットしました。その内主要なものを全て含む20件の資料の情報を入手しましたので、これから検討して行きます。
この記事では直道遺跡の住居址から馬骨が出土しているという事実を知りましたので、メモしておきます。
直道遺跡における馬骨出土の状況
「千葉市直道遺跡」(1995、財団法人千葉市文化財調査協会)から引用
説明
「この住居址で特筆すべき点は馬の骨が検出されたことである。骨の検出状況は、カマド付近を中心に住居の中央部に分布している。打ち割られたものが多く、部位がバラバラになっており、床面に密着しているもの、柱穴に落ち込んでいるもの、カマドを構築している砂質粘土の中から検出されたものなどがあり、住居を使わなくなって間もない時期に骨が残されたことを示している。また、床面の近くには焼土と灰の層があり、火熱を受けて炭化しているものも多かった。こうしたことから、食用にしたその残滓をこの住居跡に廃棄したものと考えられる。住居跡の覆土中にロームブロックを多く含む層があり、人為的に埋め戻している可能性がある。」「千葉市直道遺跡」(1995、財団法人千葉市文化財調査協会)
廃滅直後の住居址近くで人が馬を食し、その残滓をこの住居址に捨て、近くの土でその上を覆ったという状況のようです。
この付近は玄蕃所(俘囚収容所)があり軍事色が強い場所であったと考えてきています(※)が、馬骨が出土したことにより、検見川台地上で馬が使われていたことが証明されます。
この時代の馬は軍事を象徴する家畜ですから、馬骨出土は遺跡に想定される軍事的機能を傍証します。
具体的には、直道・居寒台遺跡が指す検見川台地拠点集落は単なる生活のための集落ではなく、公的軍事的機能を有する集団が居住する集落であることを傍証することになります。
※
2014.12.24記事「地名「検見川」は俘囚の検見(尋問)に由来する」参照
2014.12.24記事「花見川河口津付近の遺跡と地名」参照
……………………………………………………………………
動物遺体はリスト化されない不思議
上ノ台遺跡の住居址で牛骨出土があり、直道遺跡の住居址でも馬骨出土がありました。
何れの発掘調査報告書でも出土遺物は住居址単位に説明し、微細なものまで洩れなく住居址毎にリスト化しています。
その遺物リストには牛骨も馬骨も掲載されません。出土状況から牛骨や馬骨が「遺物」ではないと判断したからだと思います。
しかし、牛骨や馬骨が重要な考古資料であることは間違いありません。遺物リストに入れられないなら、別の出土物リストとか、考古資料リストなどをつくって掲載すればわかりやすくなります。
上ノ台遺跡の牛骨も、直道遺跡の馬骨もリスト化されていないために、結局のところ遺跡の状況を要約するときには漏れてしまっています。
そのために、その情報が重要であるにもかかわらず、報告書を事細かに調べる人以外には伝わらないことになります。
2015年3月7日土曜日
地理院地図3Dで遊ぶ
地理院地図3Dで3D地図情報をダウンロードして、地図を地形段彩図に差し替えて、地形段彩図の3D表示を楽しんでみました。
1 地形段彩
花見川流域付近の台地面の微地形を詳細に知るためにつくった次の地形段彩区分(標高13m~30mは1m毎に1色)を使ってみました。
地形段彩区分の例
2 関東西部
関東西部付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
地形段彩図にはメッシュ代替として経緯度線をオーバーレイして、3D表示した際に立体性が強調されるようにしました。
関東西部 高さ強調度30倍表示
関東西部 高さ強調度100倍表示
関東西部の台地面の地形に興味を投影すると、極端な山の姿を無視すれば、高さ強調度100倍表示の3D表示が使いやすいような印象を受けます。
3 下総
下総付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
下総 高さ強調度30倍表示
下総 高さ強調度100倍表示
下総付近台地面の地形に興味を投影すると、高さ強調度100倍表示の3D表示が、自分が思い描いているイメージと合い、使いやすいような印象を受けます。
4 花見川流域
花見川流域付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
花見川流域 高さ強調度30倍表示
花見川流域 高さ強調度100倍表示
台地面の微地形に興味を投影すると、高さ強調度30倍表示の3D表示が地形の立体性をわかりやすく表示しているように感じ、使いやすい印象を受けます。高さ強調度100倍ではデフォルメされすぎていて、使う気が起こりません。
5 4画面同時表示
Firefoxの画面を複数立ち上げてそれぞれ別の3D表示を行い、それぞれでくるくる廻したり、拡大縮小することもできます。
現在使っているモニター4枚でそれぞれ別の3D表示を行い、それぞれをいじくりまわしてみました。
4画面における地形段彩図3D表示
6 感想
地理院地図3Dの活用可能性に大きなものがあると改めて実感しました。
地理院地図3DのWEBページを見ると、地理院地図3Dの主目的が3Dプリンター対応プロジェクトのような印象を受けます。
しかし、私はブラウザ(Firefox限定)を使った地図の立体表示(とその操作性の良さ)により大きな意義があるように感じます。
空想映画で見た立体GISの一部が地理院地図3Dで実現したような印象を受けています。(2013.11.13記事「映画アバターに出てくるGIS立体投影装置」参照)
1 地形段彩
花見川流域付近の台地面の微地形を詳細に知るためにつくった次の地形段彩区分(標高13m~30mは1m毎に1色)を使ってみました。
地形段彩区分の例
2 関東西部
関東西部付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
地形段彩図にはメッシュ代替として経緯度線をオーバーレイして、3D表示した際に立体性が強調されるようにしました。
関東西部 高さ強調度30倍表示
関東西部 高さ強調度100倍表示
関東西部の台地面の地形に興味を投影すると、極端な山の姿を無視すれば、高さ強調度100倍表示の3D表示が使いやすいような印象を受けます。
3 下総
下総付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
下総 高さ強調度30倍表示
下総 高さ強調度100倍表示
下総付近台地面の地形に興味を投影すると、高さ強調度100倍表示の3D表示が、自分が思い描いているイメージと合い、使いやすいような印象を受けます。
4 花見川流域
花見川流域付近の範囲について3D表示を行ってみました。
3D表示した範囲
花見川流域 高さ強調度100倍表示
台地面の微地形に興味を投影すると、高さ強調度30倍表示の3D表示が地形の立体性をわかりやすく表示しているように感じ、使いやすい印象を受けます。高さ強調度100倍ではデフォルメされすぎていて、使う気が起こりません。
5 4画面同時表示
Firefoxの画面を複数立ち上げてそれぞれ別の3D表示を行い、それぞれでくるくる廻したり、拡大縮小することもできます。
現在使っているモニター4枚でそれぞれ別の3D表示を行い、それぞれをいじくりまわしてみました。
4画面における地形段彩図3D表示
6 感想
地理院地図3Dの活用可能性に大きなものがあると改めて実感しました。
地理院地図3DのWEBページを見ると、地理院地図3Dの主目的が3Dプリンター対応プロジェクトのような印象を受けます。
しかし、私はブラウザ(Firefox限定)を使った地図の立体表示(とその操作性の良さ)により大きな意義があるように感じます。
空想映画で見た立体GISの一部が地理院地図3Dで実現したような印象を受けています。(2013.11.13記事「映画アバターに出てくるGIS立体投影装置」参照)
2015年3月6日金曜日
上ノ台遺跡検討まとめ
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.79 上ノ台遺跡検討まとめ
上ノ台遺跡の発掘調査報告書10冊を千葉市図書館から帯出し、毎日その情報をGISに転記して解析検討してきました。
しかし図書帯出期間(延長を含めて4週間)の制限によりすでに返却してしまい、もっとたくさん検討したいことはあるのですが、キリが無いので一旦検討を締めくくることにします。
ブログの今後の活動は、近隣遺跡発掘調査報告書の閲覧検討に移ります。
この記事では、上ノ台遺跡検討をまとめ、若干の情報を追補します。
1 上ノ台遺跡(集落)の生業
上ノ台遺跡(集落)からはD地区だけで309軒、A・B地区を含めると321軒の住居趾が検出されていて古墳時代集落としては大規模です。従って、広い統治支配域を備える規模の大きな集落の人々の生業がどのようなものであったのか、興味が湧き、調べてみました。
発掘調査報告書の情報を自分なりに検討して次のような生業の様子を知ることができました。
●上ノ台遺跡(集落)生業の種別イメージ
ア 米・雑穀生産
・遺跡から米や藁が検出されている。しかし確かに米を食していたことが証明されるといった程度の検出であり、燃料はイネワラではなく野生のイネ科植物を使っている。
・近世水田開発資料から見ても水田耕作は極めて貧弱であったと考えられる。
・遺跡集落から離れた台地部で摘鎌が検出されていて、台地面での雑穀栽培が想定される。
・米・雑穀栽培は稼げる生業とはとても言えなかったと考えられる。
2015.02.19記事「上ノ台遺跡 米・雑穀栽培」参照
イ 機織
・紡錘車が16軒から16個検出されている。近隣台地で麻(あるいは桑)が栽培されていて、糸だけでなく布が生産されていたものと想定される。
・紡錘車出土住居趾からの金属製品出土が少ないことから、機織は専業的に行われていたと考えられる。
・紡錘車出土住居趾から玉類等の出土が多く、機織に従事した住居(家族)は他より富を持っていたと想定される。
・機織は稼げる生業であった可能性が高い。
2015.02.22記事「上ノ台遺跡 紡錘車出土と機織り」参照
ウ 牧畜
・1軒の住居趾内から牛骨(上顎の歯9乃至10個、下顎の歯4個、脛骨切断品1個)が検出されている。
・この検出はこの遺跡で殺牛・祭神・魚酒が行われたことを示している。
・奈良時代に隣接砂丘が浮島牛牧であったと想定されることから、古墳時代においてもその始源牛牧がすでに存在してたと考えられる。
・牛牧畜が上ノ台遺跡の稼げる生業の筆頭であった可能性がある。
・牛牧畜の現場技術は西日本を経由してやってきた集団が担っていたのではないかと仮想定した。
2015.02.24記事「上ノ台遺跡 軍需品としての牛、殺牛・祭神・魚酒」参照
2015.02.25記事「地名「幕張」の語源」参照
2015.02.27記事「地名「犢橋(コテハシ)」の語源」参照
2015.03.02記事「上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定」参照
エ 狩猟
・住居趾内から鹿骨や鉄鏃が検出されていて狩猟をおこなったことは確認できる。
・重きを置く生業であったとは考えられない。
オ 漁業
・覆土層から貝層が検出された住居趾が55軒にのぼり、廃滅住居趾がゴミ捨て場として利用された跡であると考えられる。
・ハマグリ、シオフキの出現頻度が圧倒的に高く、漁場は近くの東京湾北東岸である可能性が高い。
・貝層の分析から、貝は集落内でおかずとして利用されたもので、交易品等になることは無かったと考えられる。
・魚骨の出土は4住居趾に限定されていることから、魚骨が残るほどの中大型魚はほとんど獲られていなかったと考えられる。
・釣りや個人利用規模の網漁につかうと考えられる土錘が141軒の住居趾から出土していて、多くの住民が自らの食事用に小型魚を獲っていた可能性が高い。
・鉄釣針が2軒の住居趾から出土している。
・このような情報から、住民個人個人が行う活動により貝や小型魚が漁獲され、動動物タンパク源として重要な役割を果たしていたことが考えられるが、専業的漁業活動は低調であったと考えられる。
2015.02.17記事「上ノ台遺跡の生業と漁業活動」参照
2015.02.18記事「上ノ台遺跡 土錘出土地点分布」参照
カ 石製模造品作製
・滑石未製品が多出する住居趾が4軒あり滑石模造品作製工房であると考えられる。周辺に準工房と考えらえる住居趾もある。
・西隣するAB調査区にも3軒の滑石模造品作製工房が見つかっている。
・これらの住居趾は遺跡西側からAB地区の連続する「滑石製品作製工房地帯」を成している。
・こうした事実から、上ノ台遺跡(集落)の統治支配者(つまり花見川・浜田川流域圏の統治支配者)が自ら居住する拠点で工房をつくって滑石模造品を量産させ、統治支配地域の住民に配布して権力基盤を強化したものと想像できる。産業の一種であった。
2015.02.20記事「上ノ台遺跡 滑石模造品工房」参照
2015.02.21記事「上ノ台遺跡 玉類等出土住居趾の意義」参照
キ 鍛冶
・鍛冶関連遺物が4軒の住居趾から検出されている。
・上ノ台遺跡(集落)内で使う鉄製品を作製していたと考える。
2015.02.13記事「上ノ台遺跡報告書を閲覧し、鍛冶遺跡があることに気がつく」参照
2015.02.23記事「上ノ台遺跡 鍛冶遺物出土住居趾」参照
ク 支配統治業務
・上ノ台遺跡は前方後円墳のある東鉄砲塚古墳群対応していて、花見川・浜田川流域圏の統治拠点であったと推察している。
・掘立柱建物址は倉庫に、柱穴群は望楼に、小竪穴遺構は烽火通信施設に仮想できることから、高度な支配統治機能が存在していたと推察する。
2015.03.04記事「上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想」参照
2015.03.05記事「上ノ台遺跡 望楼(仮想)からの風景」参照
2 上ノ台遺跡の年代
「千葉・上ノ台遺跡 本編3」(千葉市教育委員会)の須恵器解説に、須恵器出土量の編年グラフが掲載されています。この編年グラフとその説明文から上ノ台遺跡のおおよその年代を知ることができます。
上ノ台遺跡時期別須恵器出土数
「千葉・上ノ台遺跡 本文編3」(1983、千葉市教育委員会)より引用、書き込み
上ノ台遺跡は出土須恵器の時期と量から、集落としてのピークは6世紀中頃と7世紀第1四半期の2回あったと考えられます。
【メモ】
上ノ台遺跡は古墳時代を最後に消滅してしまう理由は、1でまとめた上ノ台遺跡の生業の特性の中に内臓されているように思えて仕方がありません。
花見川-平戸川筋の古墳時代検討の後、奈良時代検討を行い、その時上ノ台遺跡消滅の理由がはっきりわかると思います。
現時点では上ノ台遺跡消滅は次のようにイメージしています。
古墳時代に存在した花見川・浜田川流域圏は一種の小独立国であり、現代企業社会に喩えればオーナー社長がいる中小企業みたいなものです。
律令国家が出来て中央集権的な国家体制が出来た時、花見川・浜田川流域圏は小独立国としは解体されたのだと思います。中小企業が巨大企業に吸収されてしまい、オーナー社長は支店の下の数ある出張所の所長に格下げされてしまったのだと思います。
牛牧という生産拠点や花見川河口津というインフラは蝦夷戦争における戦略的位置づけが行われ、国家中央の直轄管理下に移行したのだと思います。
国家中央から見れば、牛牧や花見川河口津はそれを現場で運営している技術集団を取り込んで直轄管理すればよいのであって、現場技術集団の上前をはねていた上ノ台遺跡(集落)は切り捨てればよかったのだと思います。
そのような激変の中で、牛牧や花見川河口津を失った上ノ台遺跡は集落としての意義を失ったのだと思います。
3 追補 滑石製品作製工房地帯
2015.02.20記事「上ノ台遺跡 滑石模造品工房」の中で、滑石製品作製工房地帯を図示しましたが、西隣A地区に発見された3軒の工房住居址の位置がわかりましたので、地図を次のように正確に書き直しました。
滑石製品作製工房地帯のイメージ(情報追補)
A地区滑石製品作製工房址の情報は「千葉市上ノ台遺跡-国鉄幕張電車基地建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-」(1973、日本国有鉄道東京第一工事局・財団法人千葉県都市公社)による
上ノ台遺跡の発掘調査報告書10冊を千葉市図書館から帯出し、毎日その情報をGISに転記して解析検討してきました。
しかし図書帯出期間(延長を含めて4週間)の制限によりすでに返却してしまい、もっとたくさん検討したいことはあるのですが、キリが無いので一旦検討を締めくくることにします。
ブログの今後の活動は、近隣遺跡発掘調査報告書の閲覧検討に移ります。
この記事では、上ノ台遺跡検討をまとめ、若干の情報を追補します。
1 上ノ台遺跡(集落)の生業
上ノ台遺跡(集落)からはD地区だけで309軒、A・B地区を含めると321軒の住居趾が検出されていて古墳時代集落としては大規模です。従って、広い統治支配域を備える規模の大きな集落の人々の生業がどのようなものであったのか、興味が湧き、調べてみました。
発掘調査報告書の情報を自分なりに検討して次のような生業の様子を知ることができました。
●上ノ台遺跡(集落)生業の種別イメージ
ア 米・雑穀生産
・遺跡から米や藁が検出されている。しかし確かに米を食していたことが証明されるといった程度の検出であり、燃料はイネワラではなく野生のイネ科植物を使っている。
・近世水田開発資料から見ても水田耕作は極めて貧弱であったと考えられる。
・遺跡集落から離れた台地部で摘鎌が検出されていて、台地面での雑穀栽培が想定される。
・米・雑穀栽培は稼げる生業とはとても言えなかったと考えられる。
2015.02.19記事「上ノ台遺跡 米・雑穀栽培」参照
イ 機織
・紡錘車が16軒から16個検出されている。近隣台地で麻(あるいは桑)が栽培されていて、糸だけでなく布が生産されていたものと想定される。
・紡錘車出土住居趾からの金属製品出土が少ないことから、機織は専業的に行われていたと考えられる。
・紡錘車出土住居趾から玉類等の出土が多く、機織に従事した住居(家族)は他より富を持っていたと想定される。
・機織は稼げる生業であった可能性が高い。
2015.02.22記事「上ノ台遺跡 紡錘車出土と機織り」参照
ウ 牧畜
・1軒の住居趾内から牛骨(上顎の歯9乃至10個、下顎の歯4個、脛骨切断品1個)が検出されている。
・この検出はこの遺跡で殺牛・祭神・魚酒が行われたことを示している。
・奈良時代に隣接砂丘が浮島牛牧であったと想定されることから、古墳時代においてもその始源牛牧がすでに存在してたと考えられる。
・牛牧畜が上ノ台遺跡の稼げる生業の筆頭であった可能性がある。
・牛牧畜の現場技術は西日本を経由してやってきた集団が担っていたのではないかと仮想定した。
2015.02.24記事「上ノ台遺跡 軍需品としての牛、殺牛・祭神・魚酒」参照
2015.02.25記事「地名「幕張」の語源」参照
2015.02.27記事「地名「犢橋(コテハシ)」の語源」参照
2015.03.02記事「上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定」参照
エ 狩猟
・住居趾内から鹿骨や鉄鏃が検出されていて狩猟をおこなったことは確認できる。
・重きを置く生業であったとは考えられない。
オ 漁業
・覆土層から貝層が検出された住居趾が55軒にのぼり、廃滅住居趾がゴミ捨て場として利用された跡であると考えられる。
・ハマグリ、シオフキの出現頻度が圧倒的に高く、漁場は近くの東京湾北東岸である可能性が高い。
・貝層の分析から、貝は集落内でおかずとして利用されたもので、交易品等になることは無かったと考えられる。
・魚骨の出土は4住居趾に限定されていることから、魚骨が残るほどの中大型魚はほとんど獲られていなかったと考えられる。
・釣りや個人利用規模の網漁につかうと考えられる土錘が141軒の住居趾から出土していて、多くの住民が自らの食事用に小型魚を獲っていた可能性が高い。
・鉄釣針が2軒の住居趾から出土している。
・このような情報から、住民個人個人が行う活動により貝や小型魚が漁獲され、動動物タンパク源として重要な役割を果たしていたことが考えられるが、専業的漁業活動は低調であったと考えられる。
2015.02.17記事「上ノ台遺跡の生業と漁業活動」参照
2015.02.18記事「上ノ台遺跡 土錘出土地点分布」参照
カ 石製模造品作製
・滑石未製品が多出する住居趾が4軒あり滑石模造品作製工房であると考えられる。周辺に準工房と考えらえる住居趾もある。
・西隣するAB調査区にも3軒の滑石模造品作製工房が見つかっている。
・これらの住居趾は遺跡西側からAB地区の連続する「滑石製品作製工房地帯」を成している。
・こうした事実から、上ノ台遺跡(集落)の統治支配者(つまり花見川・浜田川流域圏の統治支配者)が自ら居住する拠点で工房をつくって滑石模造品を量産させ、統治支配地域の住民に配布して権力基盤を強化したものと想像できる。産業の一種であった。
2015.02.20記事「上ノ台遺跡 滑石模造品工房」参照
2015.02.21記事「上ノ台遺跡 玉類等出土住居趾の意義」参照
キ 鍛冶
・鍛冶関連遺物が4軒の住居趾から検出されている。
・上ノ台遺跡(集落)内で使う鉄製品を作製していたと考える。
2015.02.13記事「上ノ台遺跡報告書を閲覧し、鍛冶遺跡があることに気がつく」参照
2015.02.23記事「上ノ台遺跡 鍛冶遺物出土住居趾」参照
ク 支配統治業務
・上ノ台遺跡は前方後円墳のある東鉄砲塚古墳群対応していて、花見川・浜田川流域圏の統治拠点であったと推察している。
・掘立柱建物址は倉庫に、柱穴群は望楼に、小竪穴遺構は烽火通信施設に仮想できることから、高度な支配統治機能が存在していたと推察する。
2015.03.04記事「上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想」参照
2015.03.05記事「上ノ台遺跡 望楼(仮想)からの風景」参照
2 上ノ台遺跡の年代
「千葉・上ノ台遺跡 本編3」(千葉市教育委員会)の須恵器解説に、須恵器出土量の編年グラフが掲載されています。この編年グラフとその説明文から上ノ台遺跡のおおよその年代を知ることができます。
上ノ台遺跡時期別須恵器出土数
「千葉・上ノ台遺跡 本文編3」(1983、千葉市教育委員会)より引用、書き込み
上ノ台遺跡は出土須恵器の時期と量から、集落としてのピークは6世紀中頃と7世紀第1四半期の2回あったと考えられます。
【メモ】
上ノ台遺跡は古墳時代を最後に消滅してしまう理由は、1でまとめた上ノ台遺跡の生業の特性の中に内臓されているように思えて仕方がありません。
花見川-平戸川筋の古墳時代検討の後、奈良時代検討を行い、その時上ノ台遺跡消滅の理由がはっきりわかると思います。
現時点では上ノ台遺跡消滅は次のようにイメージしています。
古墳時代に存在した花見川・浜田川流域圏は一種の小独立国であり、現代企業社会に喩えればオーナー社長がいる中小企業みたいなものです。
律令国家が出来て中央集権的な国家体制が出来た時、花見川・浜田川流域圏は小独立国としは解体されたのだと思います。中小企業が巨大企業に吸収されてしまい、オーナー社長は支店の下の数ある出張所の所長に格下げされてしまったのだと思います。
牛牧という生産拠点や花見川河口津というインフラは蝦夷戦争における戦略的位置づけが行われ、国家中央の直轄管理下に移行したのだと思います。
国家中央から見れば、牛牧や花見川河口津はそれを現場で運営している技術集団を取り込んで直轄管理すればよいのであって、現場技術集団の上前をはねていた上ノ台遺跡(集落)は切り捨てればよかったのだと思います。
そのような激変の中で、牛牧や花見川河口津を失った上ノ台遺跡は集落としての意義を失ったのだと思います。
3 追補 滑石製品作製工房地帯
2015.02.20記事「上ノ台遺跡 滑石模造品工房」の中で、滑石製品作製工房地帯を図示しましたが、西隣A地区に発見された3軒の工房住居址の位置がわかりましたので、地図を次のように正確に書き直しました。
滑石製品作製工房地帯のイメージ(情報追補)
A地区滑石製品作製工房址の情報は「千葉市上ノ台遺跡-国鉄幕張電車基地建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告-」(1973、日本国有鉄道東京第一工事局・財団法人千葉県都市公社)による
2015年3月5日木曜日
上ノ台遺跡 望楼(仮想)からの風景
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.78 上ノ台遺跡 望楼(仮想)からの風景
2015.03.04記事「上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想」で柱穴群が望楼、小竪穴遺構が烽火(のろし)通信施設であり、一緒に運用されていたと仮想しました。
そこで、参考に望楼からの風景画像と可視領域図を作成してみました。
柱穴群は標高16mの台地にありますが、望楼の高さを5mと仮定して、標高21mの空間から眺めた風景、可視領域図をKashmir3Dで作成しました。
上ノ台遺跡望楼(仮想)からの風景(現代地形)
Kashmir3Dで作製
5mメッシュ利用(Kashmir3Dの垂直方向地形表示最小単位は1mであるので、3D図は1m毎の段になって表示される。5mメッシュの標高表示は0.1m単位であるが、その精細さはKashmir3Dで表現できない。)
古墳時代に上ノ台と武石、検見川の台地との間における烽火通信が行われていたと考えても不合理はない風景となっています。
上ノ台遺跡望楼(仮想)からの可視領域(現代地形)
Kashmir3Dで作製
5mメッシュ利用
可視領域に上ノ台の西側台地のほとんどと幕張の砂丘全部も入り、望楼の位置は監視機能を全うできる位置にあります。
2015.03.04記事「上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想」で柱穴群が望楼、小竪穴遺構が烽火(のろし)通信施設であり、一緒に運用されていたと仮想しました。
そこで、参考に望楼からの風景画像と可視領域図を作成してみました。
柱穴群は標高16mの台地にありますが、望楼の高さを5mと仮定して、標高21mの空間から眺めた風景、可視領域図をKashmir3Dで作成しました。
上ノ台遺跡望楼(仮想)からの風景(現代地形)
Kashmir3Dで作製
5mメッシュ利用(Kashmir3Dの垂直方向地形表示最小単位は1mであるので、3D図は1m毎の段になって表示される。5mメッシュの標高表示は0.1m単位であるが、その精細さはKashmir3Dで表現できない。)
古墳時代に上ノ台と武石、検見川の台地との間における烽火通信が行われていたと考えても不合理はない風景となっています。
上ノ台遺跡望楼(仮想)からの可視領域(現代地形)
Kashmir3Dで作製
5mメッシュ利用
可視領域に上ノ台の西側台地のほとんどと幕張の砂丘全部も入り、望楼の位置は監視機能を全うできる位置にあります。
2015.03.05 今朝の花見川
早朝の風景が春らしくなってきています。
新芽が見えているわけではないのですが、木肌の色が少し変化したのかもしれません。
花見川の風景 横戸緑地下付近
花見川の風景 弁天橋から下流
花見川の風景 弁天橋から上流
横戸緑地の梅林が満開です。
紅梅
白梅
紅梅
新芽が見えているわけではないのですが、木肌の色が少し変化したのかもしれません。
花見川の風景 横戸緑地下付近
花見川の風景 弁天橋から下流
花見川の風景 弁天橋から上流
横戸緑地の梅林が満開です。
紅梅
白梅
紅梅
2015年3月4日水曜日
上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.77 上ノ台遺跡 支配統治機能に関する仮想
上ノ台遺跡の住居趾321軒は、同時にその数分の1程度が存在したと想定しても花見川流域付近では古墳時代遺跡としては巨大なものであると考えて間違いないと思います。
従って、遺跡の巨大さだけをもってしても、この遺跡に近隣地域を支配統治した機能が備わっていたと考えることができます。
さらに、上ノ台遺跡と対応する古墳が東鉄砲塚古墳群の前方後円墳であり、古墳形式から社会階層秩序をイメージするとなおさら上ノ台遺跡の支配統治機能が浮かび上がります。
古墳からみた社会階層イメージ
古墳形式からみて、花見川・浜田川流域が、東鉄砲塚古墳群(のなかの前方後円墳)を頂点とする社会階層秩序圏域に対応すると考えるイメージ。
以上から、上ノ台遺跡が花見川・浜田川流域を支配する小首長が居住するいわば首都みたいな集落であり、この集落に花見川・浜田川流域を支配統治する機能が備わっていたと考えることは当然であると考えました。
一方、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1、2、3、図版編1、2、付篇)」(千葉市教育委員会)合計6冊を4週間にわたり自宅で熱心に閲覧して、その中に支配統治機能に関連付けた記述は存在しないことを確認しました。
一度は支配統治機能の物的証拠は上ノ台遺跡報告書には記載されていないから、現段階では情報はありませんとまとめの記事に書くつもりでした。
しかし、「情報はありませんでした」と記述しようとして、本当にそうかと、意識を集中してみると、報告書の中に支配統治機能の物的証拠になり得る有力情報が存在していることに、ハタと気がつきました。
そこで、以下に上ノ台遺跡から発掘された遺構のうち支配統治機能に関連するかもしれないと考えるものについて、その仮想をメモします。
1 掘立柱建物址の支配統治機能に関する仮想
掘立柱建物址に関して、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「掘立柱建物址は6例(※)認められた。規模はさまざまで、柱間3間のものが最小、大きいものは5間である。方向は住居址の方位とほぼ一致するものが多い。時期的には、竪穴住居址関連のローム層によって埋められているものがあり、比較的古いもの、つまり、集落の前半期に属するものが主体となるようである。
構造的にみると総柱のもの2例、側柱例だけのもの2例、側柱を2列廻して間柱をもたないもの1例である。」
※報告書には5例の情報だけが掲載されているので、錯誤等であると考えます。
掘立柱建物址の分布は次の通りです。
掘立柱建物址・柱穴群・小竪穴遺構の分布
掘立柱建物址は低地から台地ののぼる道路遺構の近くで、かつ遺跡(集落)中央付近に分布します。また掘立柱建物址分布に囲まれた区域の住居址分布が疎であり、広場的空間があったような印象を受けます。
このような分布を一つの手がかりにして、次のように仮想します。
●掘立柱建物址の支配統治機能に関する仮想
・掘立柱建物址は集落の倉庫であると仮想します。
・倉庫に蓄える物品は集落が行う交易に関わるものや備蓄品であり、支配統治者が交易等を主導し、倉庫の管理権も持っていたと仮想します。
集落規模に対して倉庫を仮想する掘立柱建物址の面積が、類似遺跡例に対して大きいのか、小さいのか、残念ながら情報を持っていません。今後他遺跡事例と比較できるように情報を集めたいと思います。
2 柱穴群の支配統治機能に関する仮想
柱穴群に関して、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「柱穴群と呼んでいるものは、掘立柱群でありながら、1軒の掘立柱建物址としてまとめて理解することのできないグループをあつかっている。4群(※)認められるが、各々個性があり、建物址になるのか柵列になるのか、今のところはっきりしない。」
※報告書には3例の情報だけが掲載されているので、錯誤等であると考えます。
柱穴群の分布は上図の通りです。
柱穴群は遺跡(集落)のある台地が東側につきだしている場所、台地縁に分布してます。この場所は東京湾、牛牧が拡がる砂丘、砂丘を取り囲む検見川と武石の台地、さらに浜田川谷津とその台地を一望できます。
このような特性を手がかりにして、次のように仮想します。
●柱穴群の支配統治機能に関する仮想
・柱穴群は支配地域主部を監視する望楼址であると仮想します。
・望楼は1時期に1基存在したと考えます。
別記事で、柱穴群を望楼と見立て、そこから見える土地範囲図(可視域分布図)と立体風景図をKashmir3Dで作成し、掲載します。
参考 上ノ台遺跡付近の地形3D図
地理院地図3Dに基づいて作成
3 小竪穴遺構の支配統治機能に関する仮想
小竪穴遺構に関して、、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「小竪穴遺構は、直径2m前後の隅丸方形または、円形に近いものである。ローム層の掘り込んだ小さな竪穴状のものである。一般的には住居址に切られていることから住居址より古いものであろう。性格は、はっきりしない。出土遺物は、焼土と土師器小片である。本遺跡からは5例検出された。これもやや古手の土師器を出す竪穴住居址に切られている。」
小竪穴遺構の形状例
「千葉・上ノ台遺跡(本文編3)」(千葉市教育委員会)より引用
小竪穴遺構の分布は上図の通りです。
小竪穴遺構は柱穴群の傍に分布し、かつ焼土が出るという特性があります。
この特性から、次のように仮想します。
●小竪穴遺構の支配統治機能に関する仮想
・小竪穴遺構は狼煙(のろし)通信施設であると仮想します。
・小竪穴遺構は1時期に複数(恐らく2基)存在していて、情報量が多い狼煙(のろし)通信を行っていたと考えます。(小竪穴遺構がペアで分布しているように見えることから。)
・柱穴群(支配地域主部の監視用望楼)と小竪穴遺構(狼煙通信施設)は連動して運営されていたと考えます。
小竪穴遺構を狼煙通信施設と見立てると、類似施設(狼煙通信施設)が必ず検見川台地、武石台地に存在していたはずです。そうでなければ相互通信が成り立ちません。
今後検見川台地の遺跡(直道、居寒台、玄蕃所等)や武石遺跡等の発掘調査報告書を悉皆閲覧していきますが、見落とされている狼煙通信施設がみつかるかどうか、楽しみが増えました。
上ノ台遺跡の住居趾321軒は、同時にその数分の1程度が存在したと想定しても花見川流域付近では古墳時代遺跡としては巨大なものであると考えて間違いないと思います。
従って、遺跡の巨大さだけをもってしても、この遺跡に近隣地域を支配統治した機能が備わっていたと考えることができます。
さらに、上ノ台遺跡と対応する古墳が東鉄砲塚古墳群の前方後円墳であり、古墳形式から社会階層秩序をイメージするとなおさら上ノ台遺跡の支配統治機能が浮かび上がります。
古墳からみた社会階層イメージ
古墳形式からみて、花見川・浜田川流域が、東鉄砲塚古墳群(のなかの前方後円墳)を頂点とする社会階層秩序圏域に対応すると考えるイメージ。
以上から、上ノ台遺跡が花見川・浜田川流域を支配する小首長が居住するいわば首都みたいな集落であり、この集落に花見川・浜田川流域を支配統治する機能が備わっていたと考えることは当然であると考えました。
一方、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1、2、3、図版編1、2、付篇)」(千葉市教育委員会)合計6冊を4週間にわたり自宅で熱心に閲覧して、その中に支配統治機能に関連付けた記述は存在しないことを確認しました。
一度は支配統治機能の物的証拠は上ノ台遺跡報告書には記載されていないから、現段階では情報はありませんとまとめの記事に書くつもりでした。
しかし、「情報はありませんでした」と記述しようとして、本当にそうかと、意識を集中してみると、報告書の中に支配統治機能の物的証拠になり得る有力情報が存在していることに、ハタと気がつきました。
そこで、以下に上ノ台遺跡から発掘された遺構のうち支配統治機能に関連するかもしれないと考えるものについて、その仮想をメモします。
1 掘立柱建物址の支配統治機能に関する仮想
掘立柱建物址に関して、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「掘立柱建物址は6例(※)認められた。規模はさまざまで、柱間3間のものが最小、大きいものは5間である。方向は住居址の方位とほぼ一致するものが多い。時期的には、竪穴住居址関連のローム層によって埋められているものがあり、比較的古いもの、つまり、集落の前半期に属するものが主体となるようである。
構造的にみると総柱のもの2例、側柱例だけのもの2例、側柱を2列廻して間柱をもたないもの1例である。」
※報告書には5例の情報だけが掲載されているので、錯誤等であると考えます。
掘立柱建物址の分布は次の通りです。
掘立柱建物址・柱穴群・小竪穴遺構の分布
掘立柱建物址は低地から台地ののぼる道路遺構の近くで、かつ遺跡(集落)中央付近に分布します。また掘立柱建物址分布に囲まれた区域の住居址分布が疎であり、広場的空間があったような印象を受けます。
このような分布を一つの手がかりにして、次のように仮想します。
●掘立柱建物址の支配統治機能に関する仮想
・掘立柱建物址は集落の倉庫であると仮想します。
・倉庫に蓄える物品は集落が行う交易に関わるものや備蓄品であり、支配統治者が交易等を主導し、倉庫の管理権も持っていたと仮想します。
集落規模に対して倉庫を仮想する掘立柱建物址の面積が、類似遺跡例に対して大きいのか、小さいのか、残念ながら情報を持っていません。今後他遺跡事例と比較できるように情報を集めたいと思います。
2 柱穴群の支配統治機能に関する仮想
柱穴群に関して、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「柱穴群と呼んでいるものは、掘立柱群でありながら、1軒の掘立柱建物址としてまとめて理解することのできないグループをあつかっている。4群(※)認められるが、各々個性があり、建物址になるのか柵列になるのか、今のところはっきりしない。」
※報告書には3例の情報だけが掲載されているので、錯誤等であると考えます。
柱穴群の分布は上図の通りです。
柱穴群は遺跡(集落)のある台地が東側につきだしている場所、台地縁に分布してます。この場所は東京湾、牛牧が拡がる砂丘、砂丘を取り囲む検見川と武石の台地、さらに浜田川谷津とその台地を一望できます。
このような特性を手がかりにして、次のように仮想します。
●柱穴群の支配統治機能に関する仮想
・柱穴群は支配地域主部を監視する望楼址であると仮想します。
・望楼は1時期に1基存在したと考えます。
別記事で、柱穴群を望楼と見立て、そこから見える土地範囲図(可視域分布図)と立体風景図をKashmir3Dで作成し、掲載します。
参考 上ノ台遺跡付近の地形3D図
地理院地図3Dに基づいて作成
3 小竪穴遺構の支配統治機能に関する仮想
小竪穴遺構に関して、、「千葉・上ノ台遺跡(本文編1)」(千葉市教育委員会)では次のようにまとめています。
「小竪穴遺構は、直径2m前後の隅丸方形または、円形に近いものである。ローム層の掘り込んだ小さな竪穴状のものである。一般的には住居址に切られていることから住居址より古いものであろう。性格は、はっきりしない。出土遺物は、焼土と土師器小片である。本遺跡からは5例検出された。これもやや古手の土師器を出す竪穴住居址に切られている。」
小竪穴遺構の形状例
「千葉・上ノ台遺跡(本文編3)」(千葉市教育委員会)より引用
小竪穴遺構の分布は上図の通りです。
小竪穴遺構は柱穴群の傍に分布し、かつ焼土が出るという特性があります。
この特性から、次のように仮想します。
●小竪穴遺構の支配統治機能に関する仮想
・小竪穴遺構は狼煙(のろし)通信施設であると仮想します。
・小竪穴遺構は1時期に複数(恐らく2基)存在していて、情報量が多い狼煙(のろし)通信を行っていたと考えます。(小竪穴遺構がペアで分布しているように見えることから。)
・柱穴群(支配地域主部の監視用望楼)と小竪穴遺構(狼煙通信施設)は連動して運営されていたと考えます。
小竪穴遺構を狼煙通信施設と見立てると、類似施設(狼煙通信施設)が必ず検見川台地、武石台地に存在していたはずです。そうでなければ相互通信が成り立ちません。
今後検見川台地の遺跡(直道、居寒台、玄蕃所等)や武石遺跡等の発掘調査報告書を悉皆閲覧していきますが、見落とされている狼煙通信施設がみつかるかどうか、楽しみが増えました。
2015年3月2日月曜日
上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定
花見川地峡史-メモ・仮説集->3花見川地峡の利用・開発史> 3.4〔仮説〕律令国家の直線道路、東海道水運支路の検討>3.4.76 上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定
1 これまでの検討
・住居趾内から牛骨(上顎の歯9乃至10個、下顎の歯4個、脛骨切断品1個)が検出されています。この情報を遺跡発掘調査報告書刊行後35年経って知ったことが再発見的意義があると考えました。
2015.02.14記事「上ノ台遺跡から出土した古墳時代牛骨の重要意義」
・この検出はこの遺跡で殺牛・祭神・魚酒が行われたことを示していると考えました。
・奈良時代に隣接砂丘が浮島牛牧であったと想定されることから、古墳時代においてもその始源牛牧がすでに存在したと考えました。
2015.02.24記事「上ノ台遺跡 軍需品としての牛、殺牛・祭神・魚酒」参照
・浮島牛牧が存在した傍証として、その場所の地名「幕張」が「牧墾(マキハリ)」の音転であるという思考を示しました。
2015.02.25記事「地名「幕張」の語源」参照
・浮島牛牧が存在した傍証として、牛出荷経路上にある地名「犢橋(コテハシ)」が「特牛階(コトイハシ)」の音転であるという思考を示しました。
2015.02.27記事「地名「犢橋(コテハシ)」の語源」参照
以上の検討から、上ノ台遺跡の稼げる生業の筆頭が牛牧畜であった可能性が高いと考えるようになりました。
しかし、上ノ台遺跡から住居趾内の牛骨以外の牛牧に関連する遺物・遺構は見つかっていません。また、上ノ台遺跡と牧の場所は隣接していますが、別空間です。
また上ノ台遺跡(集落)が単純な牛飼専業集団の遺跡でないことは明白です。
そこで、今後、上ノ台遺跡(集落)と牛牧と関係の認識を深めていくための仮想定をつくりました。
この仮想定を検証しながら絶えず修正を加えて、より合理的認識を得たいと思います。
2 上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定
古墳時代の上ノ台遺跡・牛牧想定場所・関連地物の位置関係を示します。
上ノ台遺跡・牛牧想定場所・関連地物の位置関係
上ノ台遺跡と牛牧に関する社会関係を次のように仮想定します。
上ノ台遺跡と牛牧に関する社会関係の仮想定
上ノ台遺跡(集落)のリーダーの下に流域圏各地域担当の他、機織グループ、石製模造品作製グループ、米・雑穀栽培グループ、鍛冶職人、牛牧グループが属すると考えます。
リーダー及び各グループの居住地は上ノ台遺跡です。
上ノ台遺跡(集落)リーダーは東鉄砲塚古墳群内の前方後円墳に対応すると考えます。
牛牧グループの下には現場作業を担当する牛飼技術集団が存在し、その集団は牛牧推定場所に居住していたと考えます。
牛飼技術集団は上ノ台遺跡(集落)からみると社会的に下位集団であり、その集団のリーダーは愛宕山古墳に対応すると想定します。
牛飼技術集団は西方からやってきた集団(※)であると考えます。渡来人集団である可能性があります。
牛牧推定場所には柵のある牧場、厩舎・管理施設、牛飼技術集団の住居が在ったと想定します。
これまで愛宕山古墳に対応する社会的に劣位な集団は漁業とか海運に関わる集団であると想定してきました。しかし漁業とか海運に関わる劣位集団の存在が遺跡情報から見られないことや牛牧が古墳時代に重要産業であり、外来技術であり、愛宕山古墳が牛牧推定場所に存在することから、これまでの考えを変更します。
このような仮想定した社会関係が合理的なものであるかどうか、今後検証して行きたいと思います。
※牛飼技術集団が外来集団であることの傍証として、地名「犢橋」の由来をあげることができると考えています。
「コテハシ」の「コテ」の意味を中近世の花見川流域の人々は判らないで、「焼きごて」の「コテ」と取り違えたようです。一方「コテ」という言葉は西日本でよく使われる(※※)ことばのようです。従って、牛牧の牛飼技術集団は西日本を経由して房総にやってきた可能性があります。
※※(大阪弁「おんうし、おんた、こて」の解説……雄牛、牡牛。「こて」は、古語「ことい」に由来し、近畿、出雲、九州の言い方。「おんうし」は近畿と四国での言い方で、「おんた」は近畿の言い方。南関東では「おすうし」、「おうし」は点在するのみ。北関東、甲信越、北北陸で「おとこうし」、奥羽で「おとこべこ」、房総で「やろううし」、丹波、播磨以西の中国四国で「ことい」、能登で「ごって」、北琉球で「くてぃ」「うーうし」、南琉球で「びきうし」と言う。)WEB情報「大阪弁」
1 これまでの検討
・住居趾内から牛骨(上顎の歯9乃至10個、下顎の歯4個、脛骨切断品1個)が検出されています。この情報を遺跡発掘調査報告書刊行後35年経って知ったことが再発見的意義があると考えました。
2015.02.14記事「上ノ台遺跡から出土した古墳時代牛骨の重要意義」
・この検出はこの遺跡で殺牛・祭神・魚酒が行われたことを示していると考えました。
・奈良時代に隣接砂丘が浮島牛牧であったと想定されることから、古墳時代においてもその始源牛牧がすでに存在したと考えました。
2015.02.24記事「上ノ台遺跡 軍需品としての牛、殺牛・祭神・魚酒」参照
・浮島牛牧が存在した傍証として、その場所の地名「幕張」が「牧墾(マキハリ)」の音転であるという思考を示しました。
2015.02.25記事「地名「幕張」の語源」参照
・浮島牛牧が存在した傍証として、牛出荷経路上にある地名「犢橋(コテハシ)」が「特牛階(コトイハシ)」の音転であるという思考を示しました。
2015.02.27記事「地名「犢橋(コテハシ)」の語源」参照
以上の検討から、上ノ台遺跡の稼げる生業の筆頭が牛牧畜であった可能性が高いと考えるようになりました。
しかし、上ノ台遺跡から住居趾内の牛骨以外の牛牧に関連する遺物・遺構は見つかっていません。また、上ノ台遺跡と牧の場所は隣接していますが、別空間です。
また上ノ台遺跡(集落)が単純な牛飼専業集団の遺跡でないことは明白です。
そこで、今後、上ノ台遺跡(集落)と牛牧と関係の認識を深めていくための仮想定をつくりました。
この仮想定を検証しながら絶えず修正を加えて、より合理的認識を得たいと思います。
2 上ノ台遺跡と牛牧に関する仮想定
古墳時代の上ノ台遺跡・牛牧想定場所・関連地物の位置関係を示します。
上ノ台遺跡・牛牧想定場所・関連地物の位置関係
上ノ台遺跡と牛牧に関する社会関係を次のように仮想定します。
上ノ台遺跡と牛牧に関する社会関係の仮想定
上ノ台遺跡(集落)のリーダーの下に流域圏各地域担当の他、機織グループ、石製模造品作製グループ、米・雑穀栽培グループ、鍛冶職人、牛牧グループが属すると考えます。
リーダー及び各グループの居住地は上ノ台遺跡です。
上ノ台遺跡(集落)リーダーは東鉄砲塚古墳群内の前方後円墳に対応すると考えます。
牛牧グループの下には現場作業を担当する牛飼技術集団が存在し、その集団は牛牧推定場所に居住していたと考えます。
牛飼技術集団は上ノ台遺跡(集落)からみると社会的に下位集団であり、その集団のリーダーは愛宕山古墳に対応すると想定します。
牛飼技術集団は西方からやってきた集団(※)であると考えます。渡来人集団である可能性があります。
牛牧推定場所には柵のある牧場、厩舎・管理施設、牛飼技術集団の住居が在ったと想定します。
これまで愛宕山古墳に対応する社会的に劣位な集団は漁業とか海運に関わる集団であると想定してきました。しかし漁業とか海運に関わる劣位集団の存在が遺跡情報から見られないことや牛牧が古墳時代に重要産業であり、外来技術であり、愛宕山古墳が牛牧推定場所に存在することから、これまでの考えを変更します。
このような仮想定した社会関係が合理的なものであるかどうか、今後検証して行きたいと思います。
※牛飼技術集団が外来集団であることの傍証として、地名「犢橋」の由来をあげることができると考えています。
「コテハシ」の「コテ」の意味を中近世の花見川流域の人々は判らないで、「焼きごて」の「コテ」と取り違えたようです。一方「コテ」という言葉は西日本でよく使われる(※※)ことばのようです。従って、牛牧の牛飼技術集団は西日本を経由して房総にやってきた可能性があります。
※※(大阪弁「おんうし、おんた、こて」の解説……雄牛、牡牛。「こて」は、古語「ことい」に由来し、近畿、出雲、九州の言い方。「おんうし」は近畿と四国での言い方で、「おんた」は近畿の言い方。南関東では「おすうし」、「おうし」は点在するのみ。北関東、甲信越、北北陸で「おとこうし」、奥羽で「おとこべこ」、房総で「やろううし」、丹波、播磨以西の中国四国で「ことい」、能登で「ごって」、北琉球で「くてぃ」「うーうし」、南琉球で「びきうし」と言う。)WEB情報「大阪弁」
2015年3月1日日曜日
地理院地図3Dはすごい
地理院地図3Dの存在について知り2015.02.26記事「国土地理院地図の3D表示機能」で紹介しました。
地理院地図3Dでは地図や空中写真を立体的に表示して、その立体的表示を自分で自由にくるくる廻したり、拡大縮小したりしていじることが出来ます。そしてその操作がきわめてスムーズである点が際立った特徴となっています。
この地理院地図3Dが自分のブログ趣味活動(地形、地名、考古歴史)にどのように役立つか検証してみました。
自分にとっての最大興味ポイントは、地理院地図3Dに自分の作成した各種地図をオーバーレイして表示できるかどうか、その使い勝手はどうかということです。
地形、地名、考古歴史の各種情報を立体地形にプロットできれば、平面地図や平面地形段彩図に情報をプロットして得られる発想の量をさらに増大させ、質を深めることができます。思考活動を加速させることができます。それは丸4年間の活動で繰り返し体験してきたことです。
以下、地理院地図3Dに自分の作成した各種地図をオーバーレイして表示させた試行結果をメモします。
1 地理院地図3Dのダウンロードデータに情報を描き込んで表示
オフラインでブラウザ(Firefox限定)で3Dを表示するために、地理院地図3Dからデータをダウンロードすると、次の5ファイルを得ることが出来ます。
・about_pgwfile.txt…pgwファイルの説明
・dem.csv…標高データ
・index.html…起動ファイル
・texture.pgw…ワールドファイル(画像の位置ファイル)
・texture.png…画像ファイル
この内texture.pngは画像ファイルですから、一般の画像ソフトで何か描きこんで、index.htmlをFirefoxで起動すると、描きこんだ画像が立体表示されます。
2015.02.26記事「国土地理院地図の3D表示機能」ではこのような考えから、ダウンロードした画像ファイルtexture.pngに自分の作成した画像(迅速図)を張付けて表示しました。
なお、地理院地図3Dの地図や空中写真の3D表示は素晴らしいのですが、都市部では難点が生じます。例えば、花見川流域では都市化のため地図や写真の表現内容がきわめて混み合っていて、かつ台地地形です。このため、山地の場合などと較べると地形の起伏がわかりにくくなるという難点が生じます。地図や空中写真に表示される人工地物の表示が地形立体性より勝ってしまうのです。
2 地形段彩図の地理院地図3Dにおける表示と使い勝手
ダウンロードした画像ファイルtexture.pngを使わなくても、同じ範囲の地形段彩図をつくり(GIS上で切抜き)、そのファイルの名称・属性をtexture.pngにすれば、地形段彩図を地理院地図3Dで表示できるかどうか試し、成功しました。
ダウンロードデータの画像を地形段彩図画像に差し替えて3D表示が可能
地形段彩図を地理院地図3Dで表示してみると、これまでに得たことのない有力ツールとしての可能性を実感することができました。
まず、自由に角度、拡大縮小を変えることができ、それが瞬時にスムーズにできることは「すごい」と感じました。
「あそこはどうだろう」、「ここはどんな感じか」・・・という具合に自由に立体地形空間の中で物事を思考することができます。
これまで使ってきたKashmir3Dにはない操作性です。Kashmir3Dでは1枚1枚写真を撮る(画像を作成する)という一定時間を要する操作が必要です。
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 1
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 2
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 3
これからのブログ活動では、発想ツールとして地理院地図3Dを常用することになりそうです。
地形段彩図に古墳時代の遺跡分布図をプロットして地理院地図3Dで表示してみました。
地理院地図3Dを使った古墳時代遺跡分布図表示例
地形段彩とプロットされた遺跡の空間関係情報は平面図でも、この3D表示でも原理としては同じですが、私の受ける印象(図を見て生起する私の発想、連想)はまるで別情報を見ているように違ってきます。
例えば古墳時代遺跡分布と谷津との関係を考察する時に、地理院地図3Dは有力なツールとなり、またその考察結果の説明(プレゼン)の有力ツールにもなると考えます。
なお、地理院地図3Dの地形情報は10mメッシュであり、このブログで使っている5mメッシュと較べると精度が劣りますが、それがどの程度であるのか、今後検証が必要です。
また、地理院地図3Dの表示範囲は一定の区画(タイル)で行われるようになっていて自由に区画を設定できません。また3D表示を拡大すると区画の中央部に表示が収斂してしまうという特性もあります。自由に全ての範囲を拡大表示できるわけではありません。
ともあれ、地理院地図3Dを知って、その発想ツールとしての「すごさ」を実感しました。
……………………………………………………………………
【メモ】 地理院地図とGoogle earth proにおけるファイル読み込み
・地理院地図では点、線、面の書き込みができます。ファイルからKMLなどの形式で点、線、面を読み込むことができます。しかし、画像ファイルを読み込むことができません。
・Google earth proでは点、線、面の書き込みができます。ファイルからほとんどの形式で点、線、面を読み込むことができます。画像ファイルを読み込むことができます。
以上のような仕様の違いにより、地理院地図は3Dツール専用として使い、Google earth proは汎用地図ツールとして使う予定です。
地理院地図3Dでは地図や空中写真を立体的に表示して、その立体的表示を自分で自由にくるくる廻したり、拡大縮小したりしていじることが出来ます。そしてその操作がきわめてスムーズである点が際立った特徴となっています。
この地理院地図3Dが自分のブログ趣味活動(地形、地名、考古歴史)にどのように役立つか検証してみました。
自分にとっての最大興味ポイントは、地理院地図3Dに自分の作成した各種地図をオーバーレイして表示できるかどうか、その使い勝手はどうかということです。
地形、地名、考古歴史の各種情報を立体地形にプロットできれば、平面地図や平面地形段彩図に情報をプロットして得られる発想の量をさらに増大させ、質を深めることができます。思考活動を加速させることができます。それは丸4年間の活動で繰り返し体験してきたことです。
以下、地理院地図3Dに自分の作成した各種地図をオーバーレイして表示させた試行結果をメモします。
1 地理院地図3Dのダウンロードデータに情報を描き込んで表示
オフラインでブラウザ(Firefox限定)で3Dを表示するために、地理院地図3Dからデータをダウンロードすると、次の5ファイルを得ることが出来ます。
・about_pgwfile.txt…pgwファイルの説明
・dem.csv…標高データ
・index.html…起動ファイル
・texture.pgw…ワールドファイル(画像の位置ファイル)
・texture.png…画像ファイル
この内texture.pngは画像ファイルですから、一般の画像ソフトで何か描きこんで、index.htmlをFirefoxで起動すると、描きこんだ画像が立体表示されます。
2015.02.26記事「国土地理院地図の3D表示機能」ではこのような考えから、ダウンロードした画像ファイルtexture.pngに自分の作成した画像(迅速図)を張付けて表示しました。
なお、地理院地図3Dの地図や空中写真の3D表示は素晴らしいのですが、都市部では難点が生じます。例えば、花見川流域では都市化のため地図や写真の表現内容がきわめて混み合っていて、かつ台地地形です。このため、山地の場合などと較べると地形の起伏がわかりにくくなるという難点が生じます。地図や空中写真に表示される人工地物の表示が地形立体性より勝ってしまうのです。
2 地形段彩図の地理院地図3Dにおける表示と使い勝手
ダウンロードした画像ファイルtexture.pngを使わなくても、同じ範囲の地形段彩図をつくり(GIS上で切抜き)、そのファイルの名称・属性をtexture.pngにすれば、地形段彩図を地理院地図3Dで表示できるかどうか試し、成功しました。
ダウンロードデータの画像を地形段彩図画像に差し替えて3D表示が可能
地形段彩図を地理院地図3Dで表示してみると、これまでに得たことのない有力ツールとしての可能性を実感することができました。
まず、自由に角度、拡大縮小を変えることができ、それが瞬時にスムーズにできることは「すごい」と感じました。
「あそこはどうだろう」、「ここはどんな感じか」・・・という具合に自由に立体地形空間の中で物事を思考することができます。
これまで使ってきたKashmir3Dにはない操作性です。Kashmir3Dでは1枚1枚写真を撮る(画像を作成する)という一定時間を要する操作が必要です。
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 1
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 2
地理院地図3Dを使った地形段彩図表示例 3
これからのブログ活動では、発想ツールとして地理院地図3Dを常用することになりそうです。
地形段彩図に古墳時代の遺跡分布図をプロットして地理院地図3Dで表示してみました。
地理院地図3Dを使った古墳時代遺跡分布図表示例
地形段彩とプロットされた遺跡の空間関係情報は平面図でも、この3D表示でも原理としては同じですが、私の受ける印象(図を見て生起する私の発想、連想)はまるで別情報を見ているように違ってきます。
例えば古墳時代遺跡分布と谷津との関係を考察する時に、地理院地図3Dは有力なツールとなり、またその考察結果の説明(プレゼン)の有力ツールにもなると考えます。
なお、地理院地図3Dの地形情報は10mメッシュであり、このブログで使っている5mメッシュと較べると精度が劣りますが、それがどの程度であるのか、今後検証が必要です。
また、地理院地図3Dの表示範囲は一定の区画(タイル)で行われるようになっていて自由に区画を設定できません。また3D表示を拡大すると区画の中央部に表示が収斂してしまうという特性もあります。自由に全ての範囲を拡大表示できるわけではありません。
ともあれ、地理院地図3Dを知って、その発想ツールとしての「すごさ」を実感しました。
……………………………………………………………………
【メモ】 地理院地図とGoogle earth proにおけるファイル読み込み
・地理院地図では点、線、面の書き込みができます。ファイルからKMLなどの形式で点、線、面を読み込むことができます。しかし、画像ファイルを読み込むことができません。
・Google earth proでは点、線、面の書き込みができます。ファイルからほとんどの形式で点、線、面を読み込むことができます。画像ファイルを読み込むことができます。
以上のような仕様の違いにより、地理院地図は3Dツール専用として使い、Google earth proは汎用地図ツールとして使う予定です。
登録:
投稿 (Atom)