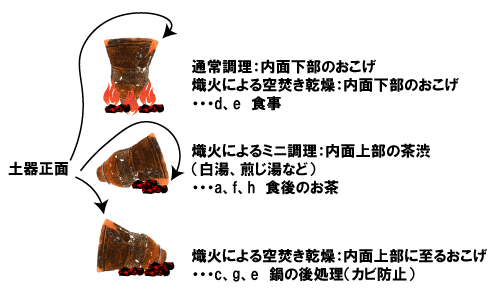現在、加曽利貝塚博物館E式土器企画展(終了)の展示土器について学習しています。この記事では加曽利EⅢ式キャリパー形土器として、加曽利EⅢ式深鉢(四街道市中山遺跡)企23土器を観察します。(企23はこのブログにおける整理番号です。)
1 加曽利EⅢ式深鉢(四街道市中山遺跡)企23 観察記録3Dモデル
加曽利EⅢ式深鉢(四街道市中山遺跡)企23 観察記録3Dモデル
撮影場所:加曽利貝塚博物館 企画展「あれもE これもE ―加曽利E式土器(印旛地域編)―」
撮影月日:2020.01.07
整理番号:企23
ガラス面越し撮影
3Dモデル写真測量ソフト 3DF Zephyr で生成 v4.523 processing 39 images
2 3Dモデルから作成した文様浮彫展開写真
GigaMesh Software Frameworkを使って3Dモデルから文様浮彫展開写真を作成しました。
3 観察と感想
・把手1と小突起3を持ちます。
・把手には二つの渦巻が縦方向につながる逆S字状の沈線文様が刻まれています。
・逆S字状渦巻沈線文様の両脇に刺突文が右3、左2あり、両側の区画文との間を隔てています。
・逆S字状渦巻沈線文様の下の胴部に円文が描かれています。把手文様が胴部にまで食い込んでいる様子として観察できます。口縁部と胴部の間のヨコ一線区画効果が著しく損なわれています。
・縦方向の逆S字状渦巻沈線文様は関東西部からの影響でしょうか?
・把手1と小突起3を持ちます。
・把手には二つの渦巻が縦方向につながる逆S字状の沈線文様が刻まれています。
・逆S字状渦巻沈線文様の両脇に刺突文が右3、左2あり、両側の区画文との間を隔てています。
・逆S字状渦巻沈線文様の下の胴部に円文が描かれています。把手文様が胴部にまで食い込んでいる様子として観察できます。口縁部と胴部の間のヨコ一線区画効果が著しく損なわれています。
・縦方向の逆S字状渦巻沈線文様は関東西部からの影響でしょうか?